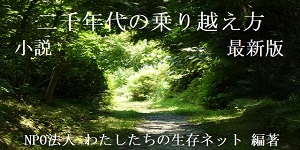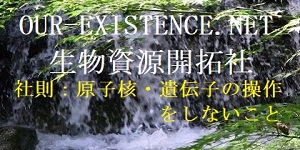COPYRIGHT(C)2000 OUR-EXISTENCE.NET ALL RIGHTS RESERVED
一歩先を行く英文法トップページ
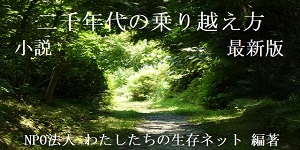
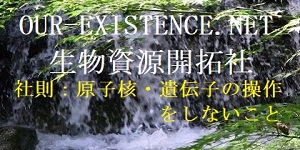
文型・文の要素
[1]文の要素
[1(文の要素と文型)]簡略化のため記号を以下の通りとする。
S:主語:状態または動作の主体を表す語句
V:動詞(助動詞を含む):状態または動作を表す語句
O:目的語:動詞が表す動作の対象を表す語句
IO:間接目的語(動作が間接的に及ぶ。「~に」に相当)
DO:直接目的語(動作が直接的に及ぶ。「~を」に相当)
C:補語(主語または目的語を説明する。原則、不可欠であり省略できない)
準補語:省略されることがあるものを準補語と呼べる。
M:(単純)修飾語(他の文の要素を修飾する語句のうち、不可欠でない、つまり、省略可能なもの)
A:付加語(他の文の要素を修飾する語句のうち、不可欠である、つまり、省略不能のもの)
これらのうち、M,を除くS,V,O,C,Aを文の要素と呼べる。
文の要素の構成によって文には以下の8文型がある。
①SV
②SVA
③SVC
④SVCA
⑤SVO
⑥SVOA
⑦SVIODO
⑧SVOC
He doesn't smoke or drink.①
彼はタバコも酒もやらない。
She lives in New York.②
彼女はニューヨークに住んでいる。
The country remained neutral.③
その国は中立でとどまった。
She is conscious of her own faults.④
彼女は自分の欠点を自覚している。
Can he prove his assertion?⑤
彼は自分の主張を証明できるだろうか。
He put the key in his pocket.⑥
彼はその鍵をポケットに入れた。
I gave the child a book.⑦
私はその子にある本を与えた。
They forced him to be silent.⑧
彼らは彼を黙らせた。
[1-1(主語)]になりえるのは以下のものである。
[1-1-1(名詞句)]主語には通常、代名詞を含む名詞句がなる。以下にそれ以外の主語になれるものを挙げる。
[1-1-2(形容詞)]
Slow and steady wins the race.
急がば回れ。
[1-1-3(副詞)]
A few months later saw the war raging.
数か月後には戦争が激しくなっていた。
[1-1-4(前置詞句)]前置詞句を主語にする文でよく現れる動詞は be, suit である。
Would after three be good for you?=
Would after three suit you?
3時過ぎはよろしいですか。
[1-1-5(引用語句、節)]引用符はあってもなくてもよい。
Warm is not the word for it.=
"Warm" is not the word for it.
暖かいなんてものじゃない。
[1-1-6(不定詞、動名詞、that節、wh節、wh+to不定詞)] it を形式主語として置くことが多い。
It is a pity that she cannot come to the party.(that節)
彼女がパーティーに来れないのは残念だ。
It isn't obvious which route would be best.(wh節)
どの道のりが一番良いか明らかでない。
It would be a big mistake for you to blame him for the accident.(不定詞)
その事故のことで彼を責めるのは君の大きな間違いだろう。
[1-2(動詞の目的語)]になりえるものは以下のものである。
[1-2-1]動詞の目的語には通常、名詞句、代名詞句がなるが、以下に動詞の目的語になるそれ以外のものを挙げる。
[1-2-2]形容詞
We didn't have very long to wait.
私たちはあまり待たなかった。
[1-2-3]副詞
She has nowhere to reside.
彼女には住むところがない。
[1-2-4]前置詞句
You have till eleven tonight.
あなたには今夜11時までの時間があります。
[1-2-5]引用句、節
Don't say "if".
「もしも」なんて言わないでくれ(仮定の話はしないでくれ)。
[1-2-6]不定詞、動名詞、that節、wh節、wh+to不定詞。
He doesn't need to work.(不定詞)
彼は働く必要がない。
I don't know what to do.(wh+to不定詞)
どうしてよいか分からない。
I don't mind waiting.(動名詞)
待つのはかまいません。
She said (that) she had broken up with him.
彼女は彼と別れたと言った。(that節)
Tell me how the war goes.(wh節)
戦況がどうなっているのか教えてください。
I found it true that he was a teacher of English.(that節、形式目的語)
彼が英語の教師であることが本当であることが分かった。
[1-2-7( IO(間接的目的語))]は物を受け取る人・動物である。その他のもの、例えば、物が運ばれる場所は間接目的語にならない。
He sent the book to me.→
He sent me the book.
彼は私にその本を送ってくれた。
He sent the book to Chicago.→
×He sent Chicago the book.
彼はシカゴに本を送った。
[1-2-8(特殊な目的語)]がある。それらをとる動詞には特徴があるので、それらを「動詞」の章で述べる。
①instrumental object
②object of result
②(1)make one's way throughタイプ
②(2)express - by -ingタイプ
③cognate object
④locative object
⑤eventive object
[1-3(補語)]
主格補語は格式体で主格、普通体・略式体で目的格。目的格補語は目的格。
It is I.(格式体)
It's me.(普通体・略式体)
それは私です。
補語になりえるのは以下のものである。
[1-3(補語になれるもの)-1(形容詞句)]
Keep quiet.(主格補語)
静かにしなさい。
They shot him dead.(目的格補語)
彼らは彼を撃ち殺した。
[1-3(補語になれるもの)-2(名詞句)]
The country is becoming a battlefield.(主格補語)
その国は戦場となりつつある。
He painted the door a dark brown.(目的格補語)
彼は戸を暗褐色に塗った。
[1-3(補語になれるもの)-2-1(属性を表す名詞句)]主語または目的語の属性を表す名詞句がそのままで補語になるのは、考えてみれば、不合理なことである。属性を表す of が省略されたと考えてもよい。
We are (of) the same /age/height/.(/年齢/身長/という属性)
私たちは/同い年だ/同じ背の高さだ/。
だが、以下では of を入れるには無理がある。
The building is ten minutes' walk.(距離という属性)
その建物はここから歩いて10分です。
You'll be a month learning them.(時間という属性)
それらを学ぶのに君は一月かかるでしょう。
[1-3(補語になれるもの)-2-2(無冠詞の可算名詞)]無冠詞の可算名詞が形容詞的に使われることがある。
He is master of himself.=
He is his own master.
彼は自立している。
[1-3-2-2-1( enough に修飾される無冠詞の可算名詞)]そのような名詞を enough が修飾すると enough は後置される。形容詞的に使われていることはそのことでも表れている。
He was fool enough to marry her.
彼は愚かにも彼女と結婚した。
以下は enough が修飾する名詞が形容詞的に使われていない例である。
There are not enough beds to shelter the refugees.
それらは難民を保護するのに十分なベッドはない。
そのように形容詞的に使われていない名詞を修飾する enough の位置は名詞の前である。
[1-3-2-2-2(具象名詞が主語に、抽象名詞が補語になった文)]は、主語が抽象名詞が表す属性をもつことを表す。ただし、(1)補語に itself が付く、または、(2-1)主語に all が付く、または、(2-2)主語と同格または副詞の all が付く、のいずれかである。
It is simplicity itself.(1)
それはいとも簡単です。
We were all curiosity.(2-2)
私たちは好奇心いっぱいだった。
All was dead silence.(2-1)
あたりは静まりかえっていた。
[1-3-2-2-2例外] perfection はそれらなしでも補語になる。
His answer was perfection.
彼の答えは完璧だった。
[1-3(補語になれるもの)-3(副詞)]
The secret was out.
その秘密は漏れていた。(主格補語)
Please put your cigarettes out.(目的格補語)
煙草の火を消してください。
[1-3(補語になれるもの)-4(前置詞句)]
This old printer is of no use to me.(主格補語)
この古いプリンターは私には役に立たない。
上は前置詞句が形容詞的に機能している。以下は副詞的に機能している。それでも補語であることに変わりはない。
A sure way to survive is by running away.
生き延びる確かな方法の一つに逃げることがある。
[1-3(補語になれるもの)-5(不定詞)]
My ambition is to won the Nobel Prize for physics.(主格補語)
私の野心はノーベル物理学賞を獲ることだ。
We urge you to vote against the bill.(目的格補語)
ぜひその法案に反対票を投じましょう。
[1-3-5-1(主語が do を含むとき)]補語になる不定詞は原型不定詞になる。
All we have to do is defend this village.
俺たちはこの村を護っていればいいんだ。
[1-3(補語になれるもの)-6(動名詞)]
Seeing is believing.(主格補語)
百聞は一見に如かず。
[1-3(補語になれるもの)-7( that節、wh節、wh+to不定詞)]
My belief is that he never tells a lie.
私が信じているのは彼が嘘をつかないということです。
In the first place, the problem is whether or not there is a resolution.
そもそも、問題は解決法があるかどうかだ。
上の文を下のようにしても意味に大差はないが、that 節が補語ではなく主語(形式主語が置かれているが)になる。
It is my belief that he never tells a lie.
In the first place, it is the problem whether or not there is a resolution.
そもそも、問題は解決法があるかどうかだ。
[1-3-7-1( (The) fact is, The truth is )] (The) fact is, The truth is の後に補語としてthat節が来るとき that は通常、省略される。また、コンマを置くことが多い。In fact, Truly のような文副詞として機能しているためである。
The (plain) truth is, I didn't know the truth.
本当のことを言って、わたしは真実を知らなかった。
[1-3-7-2(>補語が理由を表すとき)]that節を用いるかbecause節を用いるか。以下のようになる。
①The reason why ... is /that節(格式体)/because節(略式体)/.(why ... がある場合)
②/The reason/That/This/It/ is because節.(why ... がない場合)
The reason why I'm late is /that/because/ I missed the bus.
私が遅刻した理由はバスに乗り遅れたことです。
She was late. That is because she missed the bus.
彼女は遅れた。それは彼女がバスに乗り遅れたからだ。
[1-3(補語になれるもの)-7-3(/as/like/as if/as though/節)]は比較的自由に補語になる。
The situation is as you said.
状況は君の言っていたとおりだ。
His analytic method is as follows.
彼の分析方法は以下のとおりだ。
下の例文の最初の it は形式主語の it であり、二番目の it は天候などを指す it であり、文型はSV文型であり、SVC文型ではない。
It looks /as/like/as if/as though/ it's going to rain.
雨が降りそうだ。
[1-4(準主格補語)]主語を説明するが通常は削除される語を準主格補語と呼べる。準主語補語は文の要素ではない。だが、ここで準主格補語になりえるものを挙げる。
[1-4-1(形容詞句)]
The wind blew cold.
風が吹いて冷たかった。
The president left the room angry.
社長は怒って部屋を出た。
[1-4-2(分詞)]
She came running to meet me.
彼女は走って私を迎えに来た。
She awoke refreshed.
彼女はさわやかな気持ちで目を覚ました。
[1-4-3(名詞句)]
We returned to our hometown a wedded couple.
私たちは結婚して故郷に帰って来た。
He died a very rich man.
彼は大金持ちとして死んだ。
Let's part good friends.
いい友達として別れよう。
[1-4-4(混合)]
She stood there watching him, pained.
彼女は悲しそうに彼を見てそこに立っていた。
[1-5(準目的格補語)]目的語を説明するが、通常は削除される語を準目的格補語と呼べる。
The child ate the meat raw.
その子はその肉を生で食べた。
I drink coffee black.
私はコーヒーをブラックで飲む。
We can buy vegetables fresh in that farm.
その農場では野菜を新鮮な状態で買える。
First they weighed the box empty.
彼らはまず、その箱の重さを空の状態で測った。
[2]文型
[2(基本8文型)]
①SV
②SVA
③SVC
④SVCA
⑤SVO
⑥SVOA
⑦SVIODO
⑧SVOC
[2-1(SV文型)]それだけで十分な意味をもつ動詞をとる。
He can /swim/ski/cook/knit/.
彼は/泳げる/スキーができる/料理ができる/編み物ができる/。
[2-1-1( There is S 文型)] There is S 文型はこの文型に属するが、特殊なので後述する。
[2-2(SVA文型)]
[2-2-1(SVA文型とSVM文型)] SVA(Aは省略不能の付加語)の語順を崩すことができない。VAの結びつきが強く、離すことができないからである。それに対して、SVM(Mは省略可能な修飾語)型ではMSVまたはMVS(倒置)の語順が可能である。
He ran after her.(SVA)(run after で「追いかける」という意味の句動詞である)
×After her he ran.
彼は彼女を追いかけた。
After her he ran.(MSV)(この run は普通に走るという意味の動詞である)
彼女の後で彼は走った。
[2-2-2( A(付加語)を二つとる動詞もある)]
She argued with him about politics.
彼女は彼と政治について議論した。
I talked to her about myself.
私は彼女に自分のことについて話した。
[2-3(SVC文型)]をとる動詞の分類。ここでは簡単に分類するにとどめる。それぞれの詳細については「動詞」の章を参照。
①状態動詞であり、現在の状態を表す。VとCの間に to be は入らない。Cが名詞句でも入れない。be, continue, keep, remain, stay, etc.
She remained (×to be) a widow for the rest of her life.
彼女はその後もずっと未亡人で通した。
He stayed (×to be) a student all his life.
彼は一生、研究者で通した。
②知覚動詞、感覚動詞。以下に分類される。
②(1)知覚動詞。Sは知覚される物であり、Cは知覚される物の外見を表す。知覚するのは話し手である。appear, seem, look, sound, read
"How does she seem?" "She seems tired."
「彼女の様子はどうですか」「彼女は疲れている様子です」
"What does he seem?" "He seems to be a sailor."
「彼は何に見えますか」「彼は船乗りに見えます」
The sign reads, "Keep out."
その標識には「立ち入り禁止」と書いてある。
②(2)感覚動詞。Sは感覚される物であり、Cは感覚される物の外見を表す。つまり感覚するのは話し手である。feel, smell, taste
This water feels cold.
この水は冷たい。
②(3)感覚動詞。Sは感覚されるものであるとともに感覚する人間や動物であり、Cは感覚の内容を表す。
I feel bad.
私は気分が悪い。
③変化の結果を表す。進行形は「~しかけている」という意味になり変化への移行を表す。
A(形容詞句、形容詞的に機能する(補語になる)副詞句を含む)、N(名詞句)とする。
become /A/N/to不定詞/, come /A/to不定詞/, get /A/to be N/to不定詞/, go A, end up A, fall /A/N/, grow A, learn to不定詞, prove (to be) /A/N/, turn /A/N/, turn out /A/, turn out ( = prove)(to be) /A/N/, wind up /A/N/,
to be だけでなく一般のto不定詞を取れる動詞がある。ただし不定詞になる動詞は状態動詞でなければならない。ここではそのような動詞について述べる。
come to do:~するようになる
get to do:~するようになる
learn to do:~できるようになる
become to do:~できるようになる
The living in nuclear shelters would come to envy the dead on the earth.
核シェルターの中で生きている人々は地上で死んだ人々を羨むようになるだろう。
We got to know each other.
私たちは知り合いになった。
She learned to write at the age of three.
彼女は三歳で書けるようになった。
get は一時的な状態やものになることを意味する。become は持続的な状態やものになることを意味する。例えば、生物学者は持続的なものだから、
He /became/×got/×got to be/ a biologist.
彼は生物学者になった。
繰り返すが、これらの動詞がとる不定詞になる動詞は状態動詞でなければならない。例えば、
〇I came to know him aboard the ship.( know は状態動詞)
私は船上で彼と知り合った。
×I came to fight with him aboard the ship.→( fight は動作動詞でしかない)
〇I got into a fight with him aboard the ship.
私は彼と船上で喧嘩になった。
[2-4(SVCA文型)]のCAになりうるのは以下の通り
①形容詞+前置詞句
②形容詞+that節
③形容詞+(前置詞)+wh節
[2-4-1(SV+形容詞+前置詞句)]どの前置詞をとるかは形容詞によって決まっている。
I am fond of cats.
私は猫が好きだ。
She was good at mathematics.
彼女は数学が得意だ。
[2-4-2(SV+形容詞+that節)]
He was aware of her having left.→
He was aware that she had left.
彼は彼女が去ったことを知っていた。
[2-4-2-1(前置詞の欠落と復活)] SVCA文型でAがthat節のとき前置詞が欠落するが、以下のようにCとAが離れる場合は復活する。
What he was aware of is that she had left.
彼が知っていたのは彼女が去ったということだった。
What I was aghast at is that she hit him.
私が仰天したのは彼女が彼を殴ったことだ。
[2-4-3(SV+形容詞+(前置詞)+wh節)] SVCA文型でAがwh節のとき前置詞が残ることがある。
They were unsure (as to) what the next move should be.
次にどんな手を打つか彼らは確信がなかった。
[2-5(SVO文型)]⑤
[2-5(SVO文型)-1(SとOが同一→再帰代名詞)] SVO文型でSとOが同一であるときは義務的に再帰代名詞が用いられる。
He hurt himself.
彼は怪我をした。
ここで、him を使うと、別の男を怪我させたという意味になってしまう。
He hurt him.
彼はその男に怪我をさせた。
[2-5(SVO文型)-2(同格の目的語の連続)]他の文型の主語、補語、目的語にも言えることだが、同格の目的語が連なることがある。
Remember last delivery, how long it took.
前回の出産を思い出してごらん。どんなに長くかかったか。
[2-6(SVOA文型)]は、SVIODO文型に書き換えられるものと書き換えられないものに分類される。詳細は「動詞」の章で述べる。
[2-6-1(SVIODO文型に書き換えられる動詞)] give, buy など多数。SVIODO文型の節で説明する。
[2-6-2(SVIODO文型に書き換えられない動詞)]put, take, hung, inform など多数。Aとしては、前置詞句とthat節、wh節がなりえる。
Father often took me to the zoo.
父は私をよく動物園に連れて行ってくれた。
I have been reliably informed /of the couple's divorce last year/that the couple divorced last year/.
わたしはその二人が去年離婚したということを信頼できる人から聞いている。
[2-6-3(Aがthat節になるとき前置詞は省略される)]
The nutritionist informed me of the necessity to drastically change my lifestyle.→
The nutritionist informed me (×of) that I would need to drastically change my lifestyle.
その栄養士は生活スタイルを徹底的に変える必要があると私に告げた。
[2-6-4(SVOA文型での語順の変化)]Oが長い場合はAOの語順が可能である。特にOがthat節の場合はAOの語順になる。
He confessed to me that he had fallen in love with her.
彼女に恋をしたと彼は私に打ち明けた。
She spends on books much more than he spends on clothes.
彼女は服より本にはるかに多くのカネをかける。
[2-7(SVIODO文型)]は以下のように分類される。
[2-7-1( SVDO /to/for/of/ IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)]
[2-7-1-1(SVDO to IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)]つまり、前置詞 to を用いてSVOA文型に書き換えられるもの。この形をとる動詞としては give, send, lend, offer, owe, show, tell など多数ある。
[2-7-1-1(SVDO to IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)-1(受動態の作り方)] このSVIODO文型では、IO を主語にした受動態も DO を主語にした受動態も作れる。SVDO to IO 文型では DO を主語にした受動態しか作れず、IOを主語にした受動態が作れない。だから、IOが主語になるときは、SVIODOの受動態であり、to はどこにもない。また、DOが主語になるときは、SVIODOの受動態でもSVDO to IOの受動態でもありえ、IOに to を付けても付けなくてもよい。ただし、DOが主語になりIOが疑問詞になるときは to を残す。
The book was given (to) her by him.
その本は彼から彼女に与えられた。
She was given (×to) a book by him.
彼女は彼から本を与えられた。
×Who(m) was the book given by him?
〇Who(m) was the book given to by him?(前置詞残留)
〇To whom was the book given by him?(前置詞随伴)
その本は彼から誰に与えられたのか。
[2-7-1-1-2(IO を文頭に移動させるとき)]は、to を入れるのが普通である。
She told him what she had seen.→
△Him she told what she had seen.
〇To him she told what she had seen.
彼女が見たことを彼女は彼に話した。
[2-7-1-2(SVDO for IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)]つまり、前置詞 for を用いてSVOA文型に書き換えられるもの。この文型をとる動詞としては buy, make, save, spare など多数ある。
Save me some coffee.→
Save some coffee for me.
コーヒーを取って置いてくれ。
[2-7-1-2(SVDO for IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)-1(受動態の作り方)] このSVIODO文型では、IO は主語になりえるが、DO は主語になりえない。また、SVDO for IO文型でDOは主語になりえるが、IOは主語になりえない。だから、DOが主語になるときは、SVDO for IOの受動態でありIOにforを付けなければならない。また、IOが主語になるときは、SVIODO型の受動態であり、for を残してはならない。
She was bought (×for) a dress by him.
彼女は彼にドレスを買ってもらった。
×The dress was bought her by him.
〇The dress was bought for her by him.
そのドレスは彼から彼女のために買われた。
[2-7-1(SVDO of IO文型に書き換え可能なSVIODO文型)-3]つまり、前置詞 of を用いてSVOA文型に書き換えられるもの。この文型をとる動詞は現代では ask のみ。しかも DOが favor, question のときのみ可能。
He asked me three questions.→
He asked three questions of me.
彼は私に質問を3つした。
He asked her a favor.→
He asked a favor of her.
彼は彼女にお願いをした。
[2-7-1-3-1( do IO a favor )] do IO a favor で「IOに親切なことをする」の意味があるが、後者は do a favor /to/for/of/ IO への書き換えができない。以下の二文は結局、同じ意味になる。
Would you do me a favor?=
May I ask /you a favor/a favor of you/?
お願いをしていいですか。
[2-7-1-4( to, for の両方を用いて書き換えが可能な SVIODO文型)] bring, leave。ただし意味が異なる。また、この場合の for - は必須の付加部ではなく単純修飾語である。
[2-7-1-4-1( bring O /to -/for -/ )] for を用いると「~のために」と-いう意味が強くなる。
Bring me the bag here.→
Bring the bag to me here.
そのカバンをここ、わたしのところまで持って来なさい。
I've brought your heavy suitcase for you.
重いスーツケースを持って来てあげました。
[2-7-1-4-2( leave O /to/for/ - )] leave O to - では「~を~に任せる」「~を~に残して死ぬ」。leave O for - では「~を~のために取っておく」。繰り返すが、この for - は、必須の付加部ではなく、単純修飾語である。
I left some cake /for/×to/ my brother.
私は弟にケーキを残しておいた。
Her uncle left a great amount of money /to/×for/ her.
彼女の伯父は彼女に多額のカネを残して亡くなった。
I left it (up) to her which route we should take.
私はどの経路をとるか彼女に任せておいた。
[2-7-1-5( to, for, of 以外の前置詞を用いてSVOA文型に書き換えるSVIODO文型)] play DO on ID
He played me a mean trick.=
He played a mean trick on me.
彼は卑劣なたくらみを私に働いた。
[2-7-1-6( DOがthat節等のときに限ってSVIODO文型になるもの)] inform などは本来、伝達される人が目的語になり、伝達される情報は of句になるが、情報が/that節/wh節/to不定詞/wh+to不定詞/となると、前置詞 がなくなり、SVIODO型をとる。inform, remind, notify, apprise, advise
He informed me of his father's death.
He informed me that his father was dead.
彼は父親の死を私に知らせた。
This room reminds me of my father.
この部屋を見ると父のことを思い出す。
[2-7-1-6-1( advise )]には「助言する」という意味だけでなく、通知するという意味があり、前置詞として前者では /on/about/が使われ、後者では主として of が使われる。だが、後者は格式体。普通は inform, notify が使われる。
He advised me on my study.
彼は私の研究について助言してくれた。
[2-7-1-7(本来、SVOA文型だが、米のみでSVIODO文型になるもの)] provide, supply, feed, furnish, issue, present, etc.
Cows /provide/supply/ us with milk.
Cows /provide/supply/ milk to us.
Cows /provide/supply/ us milk.(米)
牛は私たちにミルクを供給する。
[2-7-1-8(疑問文に限ってSVIODO文型様のものになるもの)]。「~という言葉で~を意味する」は通常、mean - by (saying) - というSVOA文型を用いるが、疑問文に限って以下のような文型がある。
What do you mean by (saying) "Uh-huh"?(これは通常のSVOA文型)
What do you mean "Uh-huh"?(これが問題の文型)
「うんうん」ってどういう意味なの。
what は直接目的語、"Uh-huh" は引用句で間接目的語であり、これはSVIODO文型であるとも考えられる。確かにIOにDOという意味を与えるという意味が読み取れる。だが、IOが疑問詞のときのみ現れる点で苦しさがある。それに対して、by (saying) が省略されたものとも考えられる。
[2-7(SVIODO文型)-2(SVOA文型に書き換えられないもの)]take, cost, earn, wish。ただし、IO は省略可能である。
①It took her six months to complete the sculpture.
彼女がその彫刻を完成させるのに6か月かかった。
①は、
②It took six months for her to complete the sculpture.
と書き換えられるが、上の for her は to不定詞の主語である。いずれにしても上の二文の it は形式主語の it であり、主語は (for her) to complete the painting である。上の take は「~するのに~が必要である」という意味である。例えば、
In the end, it took the Japanese attack on the U.S. fleet at Perl Harbor in Hawaii on December 7, 1941 to bring the United States into the war.
結局、合衆国が参戦するには1941年12月7日のハワイの真珠湾の米艦隊への日本の攻撃が必要だった。
上の例文では to bring the United States into the war が主語である。また、上の例文のように IO は省略可能である。下は省略されていない。
It took his boots a lot longer to burn down to barely recognizable lump.
彼のブーツがそれとほぼ分からないような塊にまで燃えるのに、かなり長い時間がかかった。
This coat cost me $200.
このコートは100ドルした。
I wish you a Marry Christmas.
クリスマスおめでとう。
I wish a Merry Christmas to you.は稀である。それに対して、I wish と a を省略した Merry Christmas to you. はよくある。
[2-7(SVIODO文型)-3(二つのDOをとるもの)]以下はDOを二つ取ると考えられる。一番目のDOに概略をもってきて、二番目のDOに詳細をもってくる。envy, grudge, forgive, refuse, strike。いずれにしても、SVOA文型への書き換えは不能である。
I envy you your fortune.
私はあなたの財産がうらやましいです。
Forgive me my sin.
私の罪をお許しください。
I don't grudge him his success.
わたしは彼の成功をねたまない。
I can't refuse her anything.
彼女に頼まれたら何も断れない。
He was refused permission to the club.
彼はそのクラブへの入会を断られた.
[2-7-4(SVIODO文型かSVOA文型)]英語には新情報を後方にもってくる傾向があり、SVIODO文型、SVOA文型のどちらを用いるかはその傾向によることがある。疑問文に対する答え方もそうである。
What did she give him?
→She gave him a book.(新情報の a book を後方にもってくるためにSVIODO文型を使った)
Who did she give the book to?
→She gave the book to him.(新情報の him を後方にもってくるためにSVOA文型を使った)
What did your aunt buy for you?
→My aunt bought me a dictionary.(新情報の a dictionary を後方にもってくるためにSVIODO文型を使った)
Who did your aunt buy the dictionary for?
→My aunt bought the dictionary for me.(新情報の me を後方にもってくるためにSVOA文型を使った)
[2-X(SVO(sc)文型)]従来SVOC型と考えられていた動詞の中には、OCを一まとめとして、Oととらえてほうがよいものが多い。例えば、
I want you to do it.
私はあなたにそれをして欲しい。
は、私があなたを欲するわけではなく、you を目的語ととらえることができない。私はあなたがそれをすることを欲しているわけで、意味的に「あなたがそれをすること」が一まとまりになって目的語になっている。また、文法的にも上の例文は、
I want for you to do it.
と書き換えられる。この for は to不定詞の主語を示す記号のようなものであり、for you to do it が全体として不定詞になり、目的語となる。
また、以下のような文も可能である。
I could only see them running around.→
All I could see was them running around.
私に見えるのは彼らが走り回っているところだけだった。
上の文では them が running around という現在分詞の主語になり、them running around が意味的にまとまりをなし、文法的には主格補語になっており、間接的に動詞 see の目的語になっている。
以上のような不定詞または分詞の主語と不定詞または分詞を「小節(sc)」と呼べ、不定詞または分詞の主語を「小主語(ss)」と呼べ、不定詞または分詞を「小補語(sc)」と呼べ、それを目的語とするSVO文型を特に「SVO(sc)文型」と呼べる。
この小節(sc)は、
(1)(for)+不定詞の主語+to不定詞(for は省略可能)
(2)( for は常になし)不定詞の主語+to不定詞
(3)不定詞の主語+原型不定詞
(4)分詞の主語+現在分詞
(5)分詞の主語+過去分詞
(6)不定詞の主語+(to be)+形容詞句または名詞句または分詞( to be は省略可能)
(7)不定詞の主語+( to be は常になし)+形容詞句または名詞句または分詞
のいずれかの構造をもつ。
I want (for) you to do it.(1)
私はあなたがそれをすることを欲す。
He saw a bird flying.(4)
彼は鳥が飛ぶのを見た。
I believe him (to be) innocent.(6)
私は彼が無実であることを信じている。
以下にSVO(小節)文型をとる動詞を分類する。それぞれの詳細は「動詞」の章で述べる。
[2-X(SVO(sc)文型)-1(欲求動詞)](1)(for)+不定詞の主語+to不定詞をO(小節(sc))としてとりえる。
desire, prefer, like, love, hate, want, wish, etc.
[2-X-1(欲求動詞)-1(米略式体で for が出現する)]
He wants for me to do it.
彼はわたしがそれをすることを願っている。
[2-X-1(欲求動詞)-2(動詞と不定詞が離れると for が出現する)]英でも米の格式体・普通体でも動詞と不定詞が離れると for が出現する。
He wants very much for me to do it.
彼はわたしがそれをすることを切に願っている。
[2-X-2(認識動詞)]that節で書き換えられるO(小節(sc))をとる。(6)不定詞の主語+(to be)+形容詞句または名詞句または分詞をO(小節(sc))としてとる。
believe, consider, find, guess, know, think, understand, etc.
I found my purse gone.→
I found that my purse was gone.
私は財布がなくなっていることに気づいた。
I believe him (to be) a liar.→
I believe that he is a liar.
私は彼が嘘つきだと信じている。
[2-X-3(使役動詞)](2)(forは常になし)不定詞の主語+to不定詞、(3)不定詞の主語+原型不定詞、(4)分詞の主語+現在分詞、(5)分詞の主語+過去分詞 をO(小節)としてとりうる。make は(7)不定詞の主語+(to be は常になし)+形容詞句または名詞句または分詞をO(小節(sc))としてとりうる。make, have, get, let, cause, etc.
[2-X-3(使役動詞)-1(基本的語順からはずれることがある)]
make+分詞の主語+known → make+known+分詞の主語
let+不定詞の主語+一音節の動詞の原型不定詞 → let+原型不定詞+不定詞の主語
He let slip a very unfortunate remark.
彼はたいへんまずいことを口走ってしまった。
上の例文のように/分詞/不定詞/の主語が長いときにこれらの語順になる。
[2-X-3(使役動詞)-2(受動態)] let, have を除いて、不定詞または分詞の主語を文の主語にした受動態が作れる。その場合は原型不定詞がto不定詞になる。
They made him sign that paper.
He was made to sign that paper.
彼はその書類に署名させられた。
[2-X-4(命名動詞)]使役動詞に準じるものとしてここに分類できる。(7)不定詞の主語+(to be は常になし)+名詞句をO(小節)としてとりうる。appoint, call, elect, name, christen, etc.
They elected him the President of the United States.
人々は彼を合衆国の大統領に選んだ。
[2-X-5(感覚動詞)](3)不定詞の主語+原型不定詞、(4)分詞の主語+現在分詞、(5)分詞の主語+過去分詞を小節としてとりうる。see, hear, feel, look at, watch, notice, etc.
[2-X-5(感覚動詞)-1(受動態)]不定詞または分詞の主語を文の主語にした受動態が作れる。その場合は原型不定詞がto不定詞になる。
They saw him hit his wife.
He was seen to hit his wife.
彼は妻を殴るのを見られた。
[2-X-6(SVO(sc)文型の特徴)]以上のようなSVO(sc)文型には以下の特徴がある。
[2-X-6(SVO(sc)文型の特徴)-1( it, there が主語になれる)] it, there などの意味のない語が不定詞または分詞の主語のになれる。
Let there be light.(There be S 文型の there)
光あれ。
Look at it snow now.(天候を表す it)
今、雪が降るのを見て。
[2-X-6(SVO(sc)文型の特徴)-2(O(小節(sc))の中での態の変換が可能である)]
I want you to clear the room.→
I want the room to be cleared by you.
私は君に部屋を片付けて欲しい。
[2-X-6(SVO(sc)文型の特徴)-3(O(小節(sc))の中で倒置が起こることがある)]特に主語が長いとき。
Their negotiation made the treaty possible.
彼らの交渉のおかげでその条約が可能になった。
Their negotiation made possible the conclusion of that refined treaty.
彼らの交渉のおかげでその精妙な条約の締結が可能になった。
Those memorials kept alive remembrance of the large-scale war.
それらの記念碑がその大規模な戦争の記憶を生々しいものにする。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)] SVOC文型または前述のSVO(sc)文型に見えるものの中には実際はSVIODO型であり、DOが to 不定詞になっているものがある。advise, ask, promise, teach, tell, warn, etc.
例えば、
He advised me to wait and see.
彼は私に待機することを忠告した。
では、私が待機することを忠告するのではなく、私に待機することを忠告するのであり、me がIO間接目的語であり、to wait and see がDO直接目的語である。下の例文ではSVIODO型であることが分りやすいだろう。
He promised us not to be late again.
彼はわたしたちに二度と遅れないことを約束した。
上の例文では、二度と遅れないのは私たちではなく彼であって、us はto不定詞の主語ではない。だから、それがSVOC文型やSVO(小節)文型でないことは明らかである。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)-1(SVOA文型への書き換えはできない)]ただし、SVOA文型の書き換えはできない。その意味ではこれはやはり特殊な文型である。
She told (×to) him to leave at once.
彼女は彼にすぐに立ち去るよう言った。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)-2(that節への書き換え可→仮定法現在)]この文型ではto不定詞をthat節に書き換えることができる。後述する promise を除いて、that節の中は米では仮定法現在になり、英では should を用いる。
I advised her to wait.→
I advised her that she (should) wait.
私は彼女に待つよう忠告した。
I told him to see a doctor.→
I told him that he (should) see a doctor.
私は彼に医者に診てもらうように言った。
We recommended him to see a lawyer.→
We recommended him that he (should) see a lawyer.
私たちは彼に弁護士に相談するよう勧めた。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)-2(that節への書き換え可)-1( promose →直接法)]ただし、 promise は自ら約束するのであり、命令的要素がなく、仮定法現在またはshould節にならず、直接法になる。この意味で promise はこれらのSVIODO(to不定詞)型の中でも特殊な動詞である。
He promised me never to show up late again.→
He promised me that he would never show up late again.
彼は二度と遅刻しないことを私に約束した。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)-3(to不定詞以外も可能)]この文型をとる動詞は、DOとして、to不定詞、that節だけでなく、普通の名詞句もとれる。また、疑問詞 what、関係代名詞 what もとれる。to不定詞、that節以外をDOにとる場合は、SVOA(to IO)文型への書き換えが可能である。
What did you advise (to) him?
あなたは彼に何を助言しましたか。
He promised his grandsons the money.→
He promised the money to his grandsons.
彼は孫たちにそのカネを約束した。
"What did you ask the students?" "I asked them to attend a lecture."
「あなたは学生たちに何を求めましたか」「ある講義に出席することを求めました」
What they asked the students was to attend a lecture.
彼らが学生たちに求めたのはある講義に出席することだった。
[2-Y(SVIODO(to不定詞)文型)-4(受動態)]この文型のうちDOが名詞句であるとき to を用いてSVOA(to IO)文型に書き換えられるものでは、DOがto不定詞になるときでも IOを主語にした受動態を作ることができる。
The students were told to attend the lecture.
学生たちはその講義に出るよう言われた。
[2-8(SVOC文型)]上のSVO(sc)文型に対して、本物のSVOC型をとる動詞は以下のようなものである。
challenge, compel, dare, force, oblige, urge, allow, permit, press for, etc.
例えば、
They forced me to sign the contract.
彼らは私にその契約書に署名させた。
において、彼らは私を強制して結果として私は契約書に署名せざるをえなかったのであり、me は force の目的語ととらえられる。だから、これらの動詞は本当のSVOC型の文型をとる。また、
The US pressed for Soviet Jews to be able to emigrate.
合衆国はソ連のユダヤ人が移住できるようになるよう強く求めた。
では句動詞 press for をSVOC文型をとる動詞と見なすことができる。
[2-8-1(SVOC(準目的格補語)文型)]通常はSVO型をとるが、比較的自由にSVOC型をとる動詞が多々ある。そのような C は省略が可能であり、「準」目的格補語と呼べる。
I drink coffee black.
私はコーヒーをブラックで飲む。
She ate the meat raw.
彼女はその肉を生で食べた。
[2-9(上の8文型に当てはまらないように見えるもの)]
[2-9-1( There is S 文型)] There is S 文型はSV文型であるが、様々な点で特殊なのでここで述べる。
[2-9-1( There is S 文型)-1(定冠詞相当語句は付かない)] S は新情報になるので、S に基本的に定冠詞相当語句は付かない。
〇There was a cat in the garden.
その庭に猫がいた。
×There was the cat in the garden.→
〇The cat was in the garden.
その猫は庭にいた。
ただし、以下の例外がある。
[2-9-1( There is S 文型)-1(定冠詞相当語句は付かない)例外1]そもそも、後続する of句、関係節などに修飾され唯一のものとして限定されれば、発話の開始時点で新情報であっても、発話の終了時点では旧情報になり、定冠詞相当語が付く。そのような定冠詞相当語句の付いた名詞句は there is S 文型の S になれる。
There was the conflict between the maintenance of his family and the pursuit of his life work in his mind.
彼の心の中には家族の扶養とライフワークの追求との間の葛藤があった。
[2-9-1( There is S 文型)-1(定冠詞相当語句は付かない)例外2]定冠詞相当語句であっても、定冠詞相当でない意味をもてば、There be S 文型の S に付く。
I love espionage. Because there is this smell of adventure.(this = so, such)
私はスパイ行為が好きだ。何故なら、このような冒険の臭いがあるからだ。
[2-9-1( There is S 文型)-2(存在を表す動詞ならVになれる)] be 動詞だけでなく、存在を含意する動詞または動詞句ならVになれる。
There remains a lot to do.
まだやるべきことがたくさん残されている。
There seems (to be) no room for doubt about it.
それに疑いの余地はないようだ。
[2-9-1( There is S 文型)-3( there は文法的に主語)] there は文法的に主語として扱われ、疑問文で V there の倒置が生じる。また、不定詞、分詞、動名詞の主語になる。
It is surprising for there to be no misspelling in this long manuscript.(不定詞の主語)
この長い原稿に誤字がないのは驚きだ。
[2-9-1( There is S 文型)-4( there の併用可)] There be で純粋な存在を表し、there だけでは場所を表わさない。だから、「そこに」という意味の there と併存できる。
There were a lot of spectators there.
そこにはたくさんの見物人がいた。
[2-9-1( There is S 文型)-5( Here be S とは異なる)] Here be S は There be S と同様に見えるが、この here には「ここに」という意味がある。また、上記の文法上の特徴がなく、例えば、疑問文で以下は間違いである。
×Is here any food.→
〇Is there any food here?
ここに食べ物はありますか。
[2-9-2( This is S+分詞)]これは分詞構文の一種である。
This is Harry speaking.
こちらはハリーです。
"What's that smell?" "It is bacon burning."
「あの臭いは何だ」「ベーコンが焦げてるんです」
It's Katharine singing.
それはキャサリンが歌っているんです。
[2-9-3( It is - V )]強調構文のthatなどが省略されたものである。
It was I did it.
それをしたのは私です。
It's you're the fool.
馬鹿なのはお前だ。
[2-9-4(SVO主格補語)]分詞構文の一種である。
He left the room angry.
彼は怒って部屋を出た。
He faced his enemies naked.
彼は裸で敵に立ち向かった。
[2-9-5( thatなし節 is all )]「~だけのことだ」。that節の that が省略されたものである。
I am tired is all.
私は疲れているだけのことだ。
コンマが入ることがある。
Just give me money, is all.
カネをくれと言っているだけのことだ。
[2-9-5( thatなし節 is all )-1( all の同義語可)] all に同義語が取って代わることがある。
The man must have been out of his mind is what I think of it.
私がそれについて思うことはその男が気が狂っていたに違いないということだ。
[2-9-6(同格)]主語、補語、目的語のそれぞれの等位接続詞なしでの連続は同格である。
I remember the look of that room, how it was arranged.
その部屋の様子を思い出す。どのように物が配置されていたかを。
Remember last time, how long the delivery took.
前回を思い出してごらん。どんなに出産が長くかかったか。