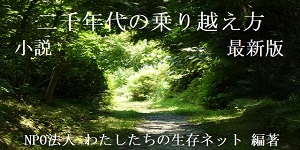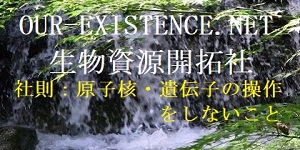COPYRIGHT(C)2000 OUR-EXISTENCE.NET ALL RIGHTS RESERVED
一歩先を行く英文法トップページ
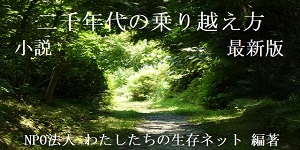
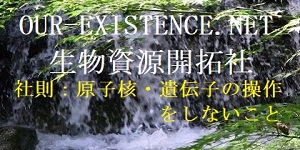
代名詞
[1]代名詞総論
[1-1(代名詞の機能の分類)]
言語外世界照応:会話、論述の外にある世界を指す。
言語内照応:会話、論述の中にある、句、節、文を指す。
逆行照応:既に述べられたことを指す。
順行照応:これから述べられることを指す。
Who is he there?(言語外世界照応)
あそこにいるあの人は誰ですか。
この例文のように、人称代名詞だからといって言語内照応とは限らない。言語外世界照応は、指示代名詞に限られず、人称代名詞にもありえる。
"What does your sister do?" "She is a dentist."(言語内照応、逆行照応)
「君のお姉さんは何をしているの」「歯医者だよ」
Let me tell you this. No one got rich raising prunes.(言語内照応、順行照応)
このことは言っておく。スモモの栽培で金持ちになった人間はいない。
[1-2(言語内照応において、先行詞と代名詞の位置関係についての規則)]次のいずれかを満たすこと。
①先行詞が代名詞に先行する。
②先行詞が主節の中に、代名詞が従属節の中にある。
③先行詞が文の要素S,V,O,C(主語、動詞、目的語、補語)のいずれかの中にあり、代名詞がそれらの修飾語の中にある。
〇If John feels good, he will go.①(先行詞が代名詞に先行する)
〇If he feels good, John will go.②(先行詞が主節の中にあり代名詞が従属節の中にある)
気分が良ければジョンは行くだろう。
×He will go if John feels good.(He が既出の John 以外の男性を指すなら間違っていないが、Johnを指すつもりなら間違い)
〇Behind him, John is hiding a weapon.③(先行詞がSであり、代名詞を含む前置詞句がVを修飾する)
ジョンは背後に武器を隠している。
×He is hiding a weapon behind John.(He が既出の John 以外の男性を指すなら間違いではないが、John を指すつもりなら間違い)
[1-2(上の規則の例外)] worry, interest, surprise などの人間の心的機能を呼び起こすことを表す他動詞では、目的語に先行詞、主語に代名詞が来て代名詞が先行することがある。目的語に特別な重心があるためである。
〇Her own face in the mirror surprised the girl.
鏡の中の自分の顔を見てその少女は驚いた。
〇Each other's health worried the villagers.
村人は互いの健康に悩んだ。
[1-3(代名詞の格)]
[1-3-1(主格補語の格)]文法的には主格だが、主格を用いるのは格式体であり、普通は目的格を用いる。
"Who is it?" "It's /I(格式体)/me(普通体)."
「誰ですか?」「私です」
[1-3-1-1(強調構文の強調部分の格)]上と同様に、普通は目的格を用いる。
It was /she(格式体)/her(普通体)/ who came.
やってきたのは彼女だった。
[1-3-2(主語だけの簡略文の格)]文法的には主格だが、普通は目的格を用いる。
"Who received the letter?" "/I did/I(格式体)/Me(普通体)/."
「誰が手紙を受け取りましたか」「私です」
[1-3-3(前置詞の目的語の格)]除外を表す前置詞 but, except を含めて前置詞の目的語の格は文法通りに目的格である。
Nobody /but/except/ him can solve the problem.(この but, except は前置詞)
彼を除いてその問題を解決できる人はいない。
[1-3-3-1( than, as の後に来る代名詞の格)]比較の対象を表す than, as についてはやや複雑である。それは than, as が前置詞と接続詞の両様に扱われるからである。だがさらに、than, as, but には関係代名詞としての用法もある。それは関係詞の章で述べる。than, as について例文を挙げながら説明する。
I like him and her. Comparatively speaking, I like her better than /him/×he/.
私は彼と彼女が好きだ。比較すると、彼より彼女が好きだ。
この場合、比較の対象が目的格だから than, as が接続詞であったとしてもその後は目的格でなければならない。
I and he like her. Comparatively speaking, I like her better than /him/he does/he/.
私と彼は彼女が好きだ。比較すると、彼が彼女が好きであるより私は彼女が好きである。
この場合、than を前置詞と考えれば、than him であり、than を接続詞と考えれば、than /he does/he/ である。いずれにしても、/than/as/の後に主語+助動詞が続くときは主格でなければならない。だが、使用頻度には差があり、目的格(略式体)→主語+助動詞(普通体)→主格(格式体)の順に頻度が小さくなる。
He is more intelligent than /her(高頻度、略式体)/she is(中頻度、普通体)/she(低頻度、格式体)/.
彼は彼女より聡明だ。
He is as intelligent as /her(高頻度、略式体)/she is(中頻度、普通体)/she(低頻度、格式体)/.
彼は彼女に劣らず聡明だ。
[1-3-3-2( you and I )] you and I が動詞や前置詞の目的語になるときは you and me となるはずである。だが、you and I に関する限りで以下のようなことが生じる。
Let you and I do it!(略式体)
Let you and me do it!(普通体、格式体)
君と僕とでやろうじゃないか。
Between you and I (普通体、略式体), it's him that invited her to our company Christmas party.
Between you and me (格式体), ....
ここだけの話だけど、会社のクリスマスパーティーに彼女を招待したのは彼なんだ。
つまり、between you and I については「ここだけの話だが」という意味で慣用句となってよく使われる。
[1-4(注意すべき代名詞の位置)]
[1-4-1(動詞→代名詞→副詞)]動詞+目的語+副詞の句動詞においては、代名詞は動詞と副詞の間に来て動詞→代名詞→副詞となる。ところで、代名詞以外の名詞句なら 動詞→名詞句→副詞 でも 動詞→副詞→名詞句 でもよい。
He took his coat and put it on hurriedly.
彼はコートを取って急いで着た。
He put /his coat on/on his coat/ hurriedly.
彼はコートを急いで着た。
[1-4-2(補語→代名詞→動詞)]補語→動詞→主語の倒置において、主語が代名詞のときは、倒置が起こらず、補語→代名詞→動詞の順になる。
Right is the gril. ⇔ Right she is.
その少女は正しい。⇔ 彼女は正しい。
[1-4-3(副詞→代名詞→動詞)]運動の方向を表す副詞→動詞→主語の倒置において、主語が代名詞のときは倒置が生じず、副詞→代名詞→動詞の順になる。
Down came the rain. ⇔ Down it came.
雨が降って来た。⇔ それが落ちて来た。
[1-4-4(代名詞→伝達動詞)]伝達動詞における 被伝達部+伝達動詞+主語の倒置において、主語が人称代名詞のときは倒置が生じない。
"Leave the snake alone," said the boy. ⇔ "Leave the snake alone," he said.
「ヘビをそっとしておいて」とその男の子は行った。⇔ 「ヘビをそっとしておいて」と彼は言った。
[1-4-5( SVIODO文型→SVOA文型)] SVIO(間接目的語)DO(直接目的語)文型においてDOが代名詞のときはSVOA(付加語)文型が好まれる。
△Give me the money.→
〇Give the money to me.
そのおカネを私にください。
△Give me it.→
〇Give it to me.
それを私にください。
[1-5(代名詞の単数形と複数形)]
[1-5-1(当然のことながら)]可算名詞単数形と不可算名詞は代名詞単数形で、可算名詞複数形は代名詞複数形で受ける。だが、単数形名詞が指していたものが複数になったときは、いきなり代名詞の複数形にすることがある。
They were shooting not just this big bomb but lots and lots of them, and we essentially did the same thing.
彼らはこの大きな爆弾を一発撃つだけでなく、何発も何発も撃っており、私たちも本質的に同じことをしていた。
[1-5-2(男も女も指しえる)]代名詞単数形、名詞単数形を受けるとき、格式体では he or she で受けるが、普通体と略式体では単数にも係らず、they で受ける。
Everybody needs to take /his or her(格式体)/their(普通体、略式体)/ own /pen/pens/.
皆、自分のペンを持って行く必要がある。
このような場合に限って、上の例文のように their を使う場合でも pen と単数形でよい。
この国では英語教師は生徒を甘やかす傾向にある。
In this country, a English teacher tend to spoil /his or her(格式体).their(普通体・略式体) students.(この場合は生徒は複数いるから students)
[2]代名詞の所有格
[2(代名詞の所有格)]一般の名詞句の所有格の意味と用法については名詞の所有格の章を参照。ここでは、そこで説明されていないことを述べる。
[2-1(特殊な意味をもつ所有格)]
[2-1-1(共有物の分配を意味する所有格)]
Now I can say my ABC.
私はもうABCが言える。
He knows his /Bible/Shakespeare/.
彼はある程度、/聖書/シャークスピア/を知っている。
I have forgotten my French.
私はフランス語を忘れた。
これらは、言語、宗教、学問、文学、芸術など人々が共有するものついて、自分への分配部分を指すと言える。専ら自分独自のものを指すわけではない。例えば、シェークスピアについて独自の解釈をしているとは限らない。だが、「それなりの」ぐらいの意味はある。
[2-1-2(~が言う~)][2-1-1]に対して、個人や集団のそれぞれが「~が考える~」、「~が言う~」などの意味をもつ所有格がある。冷笑を含むことがある。
So he is one of your "politicians."
じゃあ、彼は君らが言う「政治屋」の一人かい。
[2-2(独立所有格)]所有格が修飾する名詞句が省略されたもの。以下の場合に使用可能である。
①先行詞が代名詞に先行する。
②先行詞が主節の中に、代名詞が従属節の中にある。
③先行詞が文の要素 S,V,O,C の中にあり、代名詞がそれらの修飾語の中にある。
④先行詞が存在しないか自明の場合
My son is ten years old. How old is yours?①
私の息子は10歳です。あなたのは何歳ですか。
I wish you and yours every joy in life.(your family)④
あなたとご家族のご多幸をお祈りします。
It is yours to help him.(your duty)④
彼を助けるのは君の義務だ。
[2-2-1(独立所有格 its の頻度)] it の独立所有格 its の頻度。稀とされるが、baby, child, animalなどでありえる。
The children's health is poor except the baby's and its is perfect.
その子供たちの健康状態はよくないが、その赤ん坊は別で、申し分ない。
[2-3(二重所有格)]
英語では冠詞相当語句( a, the , this, that, some, any, no, etc. と所有格)を二つ以上重ねることがきない。所有格を除く冠詞相当語句と所有格を連ねるときは、of+独立所有格として所有格を後回しにする。その他、次の条件がある。
① ofの後は限定された人でなければならない。
② ofの前は限定されていない人または物でなければならない。
〇an opera of /his/Verdi's/(opeara に an が付き限定されていない。/his/Verdi's/は限定された人である)
/彼/ヴェルディ/のオペラ
×an opera of a composer's(a composer's は限定されていない)
〇an opera /by/of/ a composer
ある作曲家のオペラ
〇a composer's opera
×the daughter of /his/Mr. Brown's/(the daughter は限定されている)
〇the daughter of /him/Mr. Brown/
〇/his/Mr. Brown's/ daughter
/彼/ブラウンさん/の一人娘
〇a daughter of /his/Mr. Brown's/
/彼/ブラウンさん/の娘の一人
〇It is no business of yours.( no business は限定されていない)
それは君のしったことじゃない。
[2-3(二重所有格)例外]/this/that/+名詞+of+独立所有格の形をとることはある。この場合の/this/that/は「例の/よく知られた/よく話題に出ている/」という意味である。
That wife of his are coming to the party.
例の彼の妻がパーティーに来ることになっている。
[2-4(所有格+own(+名詞)]
単純な所有格と所有格+own(+名詞)は次のように対応する。例えば、our について。
所有格: our+名詞 → our own+名詞
独立所有格:ours → our own
二重所有格:名詞+of+ours → 名詞+of+our own
所有格+own(+名詞)で「自己」の意味を強めることができる。複数形では「集団のそれぞれの」の意味を含み、単に「集団の」の意味との混同を避けることができる。例えば、
We all have our own defects, and we sometimes have to face our own.
わたしたちの誰もがそれぞれの欠点をもっており、ときにはそれぞれのものに直面する必要がある。
上の例文でもし own がなければ、欠点がそれぞれの個人の欠点ではなく、人間全般の欠点ととられかねない。二番目の our own は独立所有格であり、この場合もそれぞれの個人の欠点を意味する。
[2-4-1(名詞+of+所有格+own)]名詞+of+所有格+own の二重所有格の形をとることもできる。
We sometimes have to face some defects of our own.
わたしたちはときにはそれぞれの欠点のうちのいくつかに直面する必要がある。
上の例文でも our own を用いることによって「自己のそれぞれの」が強調される。
[3]総称の代名詞
[3(総称の代名詞)]総称の代名詞としては、人称代名詞 we, you, they と広義の代名詞 one が可能である。
[3(総称)-1( one )]が総称として使われるのは格式体で古風で稀である。英では one は one で受け、米では his で受ける。
One often fails to see /one's(英)/his(米)/ own mistakes.
人は自分の間違いを見落とすことが多い。
[3-1( one )-1("I"の婉曲表現)]"I"の婉曲表現としての、one もある。これは総称ではない。
One let it pass, for one doesn't want to seem mean.
私は卑屈と思われたくないから、見逃してやった。
[3(総称)-2( they )] they は話し手と聞き手を除外する。「第三者」的なものを意味する。本当の意味での一般の人間ではない。だが、他国民、関係者、当局、権威、専門家、マスコミ…など曖昧である程度は一般的なものを指す。
They say prices will increase.(経済の専門家)
物価が上がるそうだ。
They speak Spanish in Cuba.(キューバ人)
キューバではスペイン語が話されている。
Why don't they pay nurses enough?(病院経営者)
何故、看護師に十分な給与が支払われないのだろう。
They're mending the road there.(当局、公共機関の該当部署や業者)
そこでは道路の修理が行われている。
[3(総称)-3( you )] you は話し手を除外するが、「私は別だ」ということを強調するわけでは全くない。普通体、略式体ではよく使われる。
You cannot eat your cake and have it too.(諺)
消費すれば所有することはできない。
[3(総称)-4( we )] we は you とともに日常でよく用いられるが、以下のように宣言、憲章、憲法などでも用いられる。
We the Peoples of the United Nations Determined
to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and ...(国連憲章前文冒頭)
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、…
[4] we
[4 we の分類]
① inclusive "we"(聞き手を含む)、② exclusive "we"(聞き手を含まない)、③ royal "we"、④ editorial "we", ⑤ "we" involving readers, ⑥ parental "we"
[4-1( inclusive "we")]聞き手を含む。Let's の us, Shall we -? の we が典型である。
Let's enjoy ourselves, shall we?
さあ楽しもうぜ。
[4-2( exclusive "we")]聞き手を含まない。聞き手の許可を得るときなどに用いる。
Please let us go without you.
あなたなしで私たちだけで行かせてください。
[4-3( royal "we")]ヨーロッパの宮廷で君主などが I の代わりに用いた。事実上廃用。
[4-4( editorial "we")]新聞社の編集長などが編集者など一同を指して用いる。マスメディアとしての重みをもたせる。
[4-5("we" involving readers )]著者や講演者が読者や聴衆を巻き込み、共感を喚起する。
We now turn to a different problem.
では別の問題に移ります。
[4-6( parental "we")]患者、顧客などを巻き込み、治療、サービスなどに引き入れる。
Well, how are we this morning, Ike?
やあ、アイク、今朝は調子はどう?
[5] it
[5( it の分類)]
外界照応
①事物
②性別不明の人
③時間、距離、天候…などの漠然としたもの
テキスト内照応
③逆行照応
④順行照応
[5-1(外界照応で事物を指す it)]
It happened so quickly.
それは急に起こった。
[5-2(外界照応で性別がない物または性別不明の人を指す it)]
There's the doorbell. It must be a police officer.
玄関のベルが鳴っている。警官に違いない。
[5-3(外界照応で時間、距離、天候…などの漠然としたものを指す it)]
It was a quarter to twelve.(時間)
12時15分前だった。
It's Sunday tomorrow.(時間)
明日は日曜日だ。
It was the first time /that/when/ such a privilege had been accorded him.(時間を指すのであって、強調構文ではない)
それはそのような特権が彼に与えられた初めてのときだった。
It is /raining/snowing/.(天候)
/雨/雪/が降っている。
How far is it to Paris.(距離)
パリまでどれくらいありますか。
Do you like it here?(風土)
あなたはここが気に入りましたか。
It's all up with him.(状況全般)
彼はどうしようもない。
[5-3-1(慣用表現)]代表的なものだけを挙げる。
catch it:罰を受ける、叱られる
You'll catch it for breaking the window.
窓ガラスを割ってしかられるぞ。
foot it:(長い距離を)歩く
I will foot it home.
私は歩いて家に帰ろう。
make it:成功する、うまくやる、たどりつく
He couldn't make it in business.
彼は商売で成功しなかった.
I made it on time.
時間通りにそこに着いた。
[5-4(テキスト内照応、逆行照応の it )]先行の句または節または文を受ける。
He bought a car. It's a Ford.
彼は車を買った。フォードの車だ。
[5-4-1(性別のないものを表す単数可算名詞、(物質名詞、抽象名詞を含む)不可算名詞)]、擬人化されていない動物、性別不明または性別を記すことが不要の乳幼児、子供を受けられる。
Beauty is everywhere and it makes us happy.
美はいたるところにあり、私たちを幸せにする。
ただし、抽象的概念は女性扱いにして以下のようにすることがある。
Beauty is everywhere and she makes us happy.
The child is crying, isn't it?
あの子は泣いているのではありませんか。
[5-4-2(先行する文、節、句を受けられる)]
Tomorrow will be fine. No one doubts it.(文を受ける)
明日は晴れだろう。誰もそれを疑わない。
He can't drive a car. Neither can she do it.( do it で動詞句を受ける)
彼は車の運転ができない。彼女もできない。
She is intelligent, though she doesn't look it.(形容詞句を受ける)
彼女は、そうは見えないが、賢い。
[5-4-2(例外)]前の疑問文を目的語として受けるには /it/this/that/which/ は不要である。それらを入れても間違いではないが。
"Who said it?" "I don't know (/who said it/△it/)."
「誰がそう言ったの」「知らない」
[5-5(テキスト内照応、順行照応の it )]
[5-5-1(順行照応の it は形式主語または形式目的語)]として機能することが多い。it で受けるべき部分とそれ以外を比較して、それ以外が長い場合、形式主語は用いられない。下の文程度の割合では形式主語 it を用いても用いなくてもよい。他方、形式目的語 it は義務的に用いられる。
That she would be on time could hardly be expected.
It could hardly be expected (that) she would be on time.
彼女が間に合うことはほとんど期待できなかった。
上の一番目の文のように、That節が文頭に来た場合、that は省略できない。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)]
①通常の名詞句
②to不定詞
③動名詞
④that節
⑤wh節(疑問詞節)
⑥if節(⑤wh節と異なり、仮定の接続詞 if が導く節)
⑦when節(⑤と異なり、時の接続詞 when が導く節
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-1(通常の名詞句)]要素の移動の章で説明される「右方転移」の一種である。名詞句の前にコンマが置かれることが多い。
It is the ideal place in which to think, a railway carriage.
列車の中はものを考えるのに理想的な場所だ。
It is amazing the belief they have in one another.
彼らが互いに寄せている信頼は驚くべきだ。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-2( to不定詞)]
These are situations which it is difficult to explain.
これらは説明しにくい状況だ。
You don't know what it is to be poor.
君は貧乏であることがどういうものか知らない。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-3(動名詞)]難易、無駄、無意味、感情的判断を強調する場合に用いられる。それら以外ではかなり略式体。動名詞の前にコンマが置かれると容認されることが多い。
It is difficult making new friends.(難易)
新しい友達をつくることは難しい。
It is nice being with you.(感情的判断)
あなたと一緒にいると楽しい。
It is no use his apologizing.(無駄)
彼が謝っても無駄です。
It was so easy being with him.(難易)
彼と一緒に居ると気楽だった。
It would be surprising, your being able to find a new job.(コンマがある)
君に新しい仕事が見つかったら驚きだ。
It's tough being a man.(難易)
男はつらいよ。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-4( that節)]
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-4( that節)-1( It is の省略)] It isが省略されることがある。
Small wonder that he decided to take no part in the debate.
彼がその議論に参加しないことに決めたことは大きな驚きではない。
[5-5-2-4( that節)-2(主観的判断、感情的判断→ should )]主観的判断、感情的判断であることを敢えて示す場合、should を用いることがある。そうでなければ、直接法を用いる。
It's a pity that you should have to go home so soon.
あなたがすぐに帰宅しなければならないことが残念です。
[5-5-2-4( that節)-3(広義の命令表現)] It is necessary that- などの広義の命令表現では、アメリカ英語では仮定法現在(動詞の原型)、イギリス英語では should を用いる。
It is necessary /for him to prepare for the worst/that he (should) prepare for the worst.
彼は最悪の事態に備えておく必要がある。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-5( wh節)]
It is still a mystery why he killed himself.
彼が何故自殺したかいまだ謎だ。
[5-5-2(形式主語 it が受けるもの)-6,7( if -, when - )] 仮定の接続詞 if が導く節。時の接続詞 when が導く節
It will bewilder everybody /if/when/ they are uncertain where to run.
どこに逃げたらよいか分からない/場合/時/は誰もうろたえるだろう。
[5-5-3(形式目的語の it が受けるもの)]形式主語と異なり、形式目的語 it は義務的に用いられる。形式目的語 it が受けるのは以下のとおりである。
①to不定詞
②動名詞
③that節
④wh節(疑問詞節)
⑤if節(④wh節と異なり、仮定の接続詞 if)
⑥when節(④と異なり、時の接続詞 when
He felt it his duty to visit her in hospital.①
彼は彼女を見舞うのは自分の義務だと感じた。
I thought it pointless starting before eight o'clock.②
8時前に発つのは意味がないと思った。
I'd consider it a compliment if you accepted.⑤(仮定の接続詞 if)
お受けいただければ光栄です。
I will leave it to you to decide.①
私は決定を君に任せる。
[5-5-3-1(SVOC文型でもSVO(sc)文型でもSVO文型でも)] SVOC文型のOまたはSVO(sc)文型の小節の中の小主語が/to不定詞/動名詞/that節/wh節/if節/when節/であるときに、it はそれらを義務的に代用する。さらに、SVO文型において、Vが通常は/that節/wh節/if節/when節/をOとしないときで、敢えてそれらを目的語とする場合は、形式目的語 it を義務的に置く。
I don't like it that you were there.=
I don't like the fact that you were there.
私は君がそこにいたのが気に入らない。
She loved it that he made all the decisions.=
She loved the fact that he made all the decisions.
彼女は彼が何でも決定してくれるのが有り難かった。
I can't help it if you think I'm odd.=
I can't help the case that you think I'm odd.
君が僕のことを変人だと思っても僕はどうしようもない。
She hated it when her mother acted like that.=
She hated the case that her mother acted like that.
彼女は母親がそのように振る舞うのが嫌いだった。
それらに対して、say, think, know, remember, etc は普通にthat節等を目的語としてとるので、形式目的語it を入れてはいけない。
She knew (×it ) that she was being followed.
彼女は後をつけられていることを知っていた。
[5-5-3-2( Depend upon it )]は「きっと」という意味の慣用句である。
Depend upon it, the book will be a best-seller.
間違いなく、その本はベストセラーになる。
[5-5-4(強調構文において)]It is X that関係詞節の形でthat節の中の主語、動詞の目的語、前置詞の目的語、副詞句、副詞節をXとして強調することができる。Xは新情報である。通常、新情報は後方に置かれるが、強調構文は新情報を前方において強調する。
He broke the window with a stone yesterday.→
彼は昨日、石でその窓を割った。
It was /him/he/ /that/who/ broke the window with a stone yesterday.(主語)
It was the window that he broke with a stone yesterday.(動詞の目的語)
It was a stone that he broke the window with yesterday.(前置詞の目的語)
It was with a stone that he broke the window yesterday.(副詞句)
It was yesterday that he broke the window with a stone.(副詞句)
It was when I was in Berlin that I first met her.(副詞節)
彼女と初めて会ったのは私がベルリンに居たときだった。
It was because I was in Berlin then that I could not meet her.(副詞節)
彼女と会えなかったのは私がそのときベルリンに居たからだった。
[5-5-4(強調構文における)-1(関係詞)]は何でもよい。that が用いられることが多い。強調するものが人であるときは who が用いることが多い。それは一般の関係詞と同様である。
It is /I/me/ who am to blame.
悪いのは私です。
[5-5-4(強調構文における)-2(関係詞の省略)]関係詞が主格になる場合を含めて、関係詞は省略されえる。
It is I (/that/who/) am to blame.
悪いのは私です。
[5-5-4-3(疑問詞さえも強調部分になりえる)]
Who is it that is to blame?
悪いのは誰だ。
[5-5(テキスト内照応、順行照応の it )-5(慣用句)]
[5-5-5-1( Depend upon it, 節)]「きっと」
Depend upon it, the book will be a best-seller.
その本は間違いなくベストセラーになる。
[5-5-5-2( see to it that節)]「気を付けて~する」
See to it that this doesn't happen again.
こんなことが二度と起こらぬよう気をつけなさい。
[6]再帰代名詞
[6(再帰代名詞の構造)]
| 単数 | 複数 |
| 一人称 | myself | ourselves |
| 二人称 | yourself | yourselves |
| 三人称 | himself
herself
itself | themselves |
代名詞所有格+形容詞+self(selves)の形も可能だが、これは再帰代名詞ではなく、文字通り「~な自己」を意味する。
My mother gave her whole self to her job.
母は仕事に自分のすべてを捧げていた。
Her father was /his/×him/ usual discreet self.
彼女の父親はいつもの慎重な彼だった。
[6-1(再帰代名詞の用法の分類)]
[再帰用法]
①再帰動詞(再帰代名詞の使用が義務的であるもの)において
②準再帰動詞(再帰代名詞を省略して自動詞化することが可能であるもの)において
③一般の動詞において
[強意用法]
[6-1-1(再帰用法)]主語と動詞の目的語または前置詞の目的語が同一である、または、動詞または前置詞の目的語と別のそれらが同一である場合の用法である。
[6-1-1-1(再帰動詞)](再帰代名詞の使用が義務的であるもの)において
You should avail yourself of every chance to improve your English.
あなたは英語力を伸ばすあらゆる機会を利用するべきだ。
I betook myself to London.
私はロンドンに行った。
He absented himself from the meeting.
彼はその会合を欠席した。
He prides himself on his driving skill.
彼は自分の運転技術を自慢している。
[6-1-1-2(準再帰動詞)]準再帰動詞(再帰代名詞を省略して自動詞化することが可能であるもの)において
Behave (yourself) now!
さあ、行儀よくしなさい。
I won't oversleep (myself).
私は寝過ごさないつもりだ。
adjust (oneself) to one's new way of life
新しい生活様式に慣れる
prepare (oneself) /for/to accept/ defeat
/敗北の/敗北を受け入れる/覚悟をする
[6-1-1-2-1(準準再帰動詞))]上の二つの例文は一般の目的語をとる動詞が再帰代名詞をとって特別な意味を生じたものであり、「準準再帰動詞」と呼べる。
adjust the seat to one's height
自分の身長に合うように座席を調節する
[6-1-1(再帰用法)-3(一般の動詞において)]上のような特殊な動詞ではなく、一般の動詞において、再帰代名詞が他動詞の目的語または前置詞の目的語になることがある。このとき、以下の条件がある。下の条件を満たすときは再帰代名詞を使用したほうがよい。そうしないと、指すものが別もの、別人と誤解される恐れがある。
①先行詞と再帰代名詞は一つの単文または節(小節を含む)の中になければならない。
②先行詞が先行しなければならない。
〇He talked to her about himself.(単文の中で主語と前置詞の目的語が同一)
彼は彼女に自分のことを話した。
〇He talked to her about herself.(単文の中で前置詞の目的語と別の前置詞の目的語が同一)
彼は彼女に彼女のことを話した。
〇He thought that she admired herself.(that節の中で主語と動詞の目的語が同一)
彼は彼女が自賛していると思った。
×He thought that she admired her.(her では別の女性を敬愛しているという意味になってしまう)
〇He thought that she admired him.
彼は彼女が彼のことを敬愛していると思った。
×He thought that she admired himself.(that節の中で主語と動詞の目的語が同一でない)
彼は彼女が彼のことを敬愛していると思った。
〇He wanted her to wash herself.(her to wash herself は小節であり、小節の中で主語と動詞の目的語が同一)
彼は彼女に彼女の手を洗って欲しかった。
〇He wanted her to wash him.
彼は彼女に彼の手を洗って欲しかった。
×He wanted her to wash ×himself.(小節の中で主語と動詞の目的語が同一でない)
〇He shaved himself.
彼は髭を剃った。
×Himself was shaved by him.(先行詞が再帰代名詞より前にない)
He seemed to her to admire /himself/×him/×herself/.
(全体を SVC型の単文と見なせ、主語とCの中の動詞の目的語が同一である。to her は単なる修飾語でしかない)
彼はうぬぼれているように彼女には思われた。
[6-1-1-3例外( I→me, you→you )]だが、I→me, you→you, など誤解の生じようのないときは普通の代名詞を用いてもよい。
Like a bridge over troubled water. I will lay me down.(Simon & Garfunkel)
荒れた水面に架かる橋のように。私は横たわろう。
[6-1-1(再帰用法)-3(一般の動詞において)-1(再帰代名詞が前置詞の目的語になる特別な条件)]だが、再帰代名詞が前置詞の目的語になるときは上の一般的な条件だけでなく以下のような特別な条件がある。
[前置詞に関する限りで再帰代名詞を用いる特別な条件]
③再帰代名詞が句動詞の目的語になる。④再帰代名詞が他動詞と同語源の名詞の補部(目的語に相当するもの)になる。⑤前置詞が目的、方向を表すとき。⑥場所などを表す前置詞が比喩的で心的なものを指すとき。
[前置詞に関する限りで普通の代名詞を用いる特別な条件]
⑦動詞が運動を表さず前置詞が場所・時間を表すときは、再帰代名詞ではなく普通の代名詞を用いる。
それら以外についてはどちらでもよい。
She can look after herself.③
彼女は一人暮らしができる。
I did not know what to do with myself.③
私はどうしたらいいか分からなかった。
He thinks too much of himself.③
彼は自分を高く評価し過ぎる。
She heard a criticism of herself.④( ciricism は他動詞 criticize と同語源)
彼女は自分に対する批判を耳にした。
He gave her a photograph of /himself/herself/.④(photograph は他動詞 photograph と同語源)
彼は彼女に/自分/彼女/の写真をあげた。
I kept it for myself.⑤(目的)
私はそれを自分のために取って置いた。
She was talking to herself.⑤(方向)
彼女は独り言を言っていた。
He aimed the gun at himself.⑤(方向)
彼は自分に銃を向けた。
She was beside herself with rage.⑥(心的)
彼女は怒りで我を忘れていた。
He winced within himself.⑥(心的)
彼は心の中でびくっとした。
Have you any money on you?⑦(動詞が運動を表さず前置詞が場所を表す)
おカネの持ち合わせがありますか。
She had her fiance besides her.⑦(動詞が運動を表さず前置詞が場所を表す)
彼女は婚約者をそばにはべらせていた。
We have the whole day before us.⑦(動詞が運動を表さず前置詞が時間を表す)
これからまる一日ある。
He saw a reptile near him.⑦(動詞が運動を表さず前置詞が場所を表す)
彼は近くで爬虫類を見かけた。
I pulled the covers over /me/myself/.⑤(動詞が運動を表す)
私はカバーを体の上に引き寄せた。
I tied the rope around /me/myself/.⑤(動詞が運動を表す)
私はロープを体に巻き付けた。
I drove the flies away from /me/myself/.(動詞が運動を表す)
私はハエを体から追い払った。
[6-1-2(強意用法)]
[6-1-2(強意用法)-1(主語を強調するとき)]主語の後または中位または文末に置く。
I myself have never been there.(主語の後)
I have never myself been there.(中位で否定語の後)
I've never been there myself.(文末)
私自身はそこへ行ったことが一度もない。
[6-1-2(強意用法)-2(目的語、補語を強調するとき)]それらの後に置く。
I spoke to the manager himself.(目的語の後)
私は支配人自身と話した。
She was kindness itself.(補語の後)
彼女は親切そのものだ。
[6(再帰代名詞)-2(慣用的表現)]
[6-2-1( to oneself )]「一人で~する」を意味する。
[6-2-1-1]伝達動詞において、以下の動詞は「独り言を言う」「一人でほくそ笑む」などの意味になる。
talk, speak, mutter,
sing,
laugh, smile, chucle,
frown,
それらに対して、say to oneselfは「心の中で思う」「自分に言い聞かせる」を意味する。
[6-2-2( by oneself )]この by は「~のそばに」の意味であり、by oneself で「自分のそばに」→「一人で」の意味になる。また、by には「~によって」(方法・手段)の意味があり、「自分によって」→「独力で」の意味になる。
The old man lives (all) by himself.
その老人はひとり暮らしです。
I did the whole of the work by myself.
私はその仕事を全部自分でやった.
[6-2-3( for oneself )]この for は「~のために」の意味であり、for oneself で「そのもののために」という意味になる。さらに発展して「一人で」「独力で」の意味にもなる。
That is your problem. You have to figure out how to solve it for yourself.
それはあなたの問題です。独力でどう解決するかを見つけ出さなければなりません。
I want to be able to do things for myself by myself.
私は自分のことを自分でできるようになりたい。
He values labor for itself.
彼は労働そのものに価値をおく。
[6-2-4( of oneself )]この of は「~から」の意味であり、of oneself で「ひとりでに」「自ずと」を意味する。だが、古語であり、現代では by oneself を用いる。つまり、by oneself には「ひとりでに」「自ずと」の意味もある。
The bleeding stopped by itself.
出血は自ずと止まった.
[6-2-5( in oneself )]「それ自体」を意味する。前置詞なしの oneself でも同意のことがある。また、as such なども同意のことがある。
The free competition between economic powers does not matter in itself. What matters is the collusion between them and that between them and political powers.
経済的権力の間の自由競争はそれ自体では問題にならない。問題になるのは政治的権力の間及び経済的権力と政治的権力の間の癒着だ。
[7]指示代名詞
[7-1(外界照応の this, these, that, those)]
[7-1-1(使い分け)]現実世界の話し手の領域または聞き手の領域または第三者の領域にあるものを指す。物質的身体的空間的領域(例えば、実際に手に持っている)だけでなく、心理的領域においても以下のことが言える。
| 話し手 | 聞き手 | それらの外(第三者) |
| 日本語 | これ、これら | それ、それら | あれ、あれら |
| 英語 | this, these | that, those | that, those |
つまり、日本語の「それ」と「あれ」の区別は英語にはない。
This is Betty, Mum.(電話で話し手の領域→this)
もしもし、ベティだよ。お母さん。
Give me that filthy lollipop! Don't put it in your mouth.(聞き手の領域→that)
その汚いキャンディーをよこしなさい。それを口に入れてはいけません。
Don't talk to your mother like that.(聞き手の領域→that)
お母さんに向かってそんな口のきき方をするものではありません。
That is the Statue of Liberty over there.(第三者の領域→that)
あちらに見えますのが自由の女神像でございます。
The bell rang. "That's her," they said with one voice.(第三者の領域→that)
ベルが鳴った。彼らは一斉に「あれは彼女だ」と言った。
I used to enjoy those enormous hotel breakfasts.(第三者の領域→those)
かつて私はあの盛りだくさんのホテルの朝食を楽しんだものだ。
That Bach had genius.(第三者の領域→that)
あのバッハは天才だった。
[7-1-2(主観、感情)]だが、英語の this, these, that, those の区別は日本語のものよりかなり主観的で感情的である。聞き手の領域にあっても、話し手がそれは自分のものだと思えば this, these を用いることは多々ある。また、that, those は修飾する語に嫌悪などの陰性感情を込めることがある。心理的な領域に入れたくないという心情からである。
She is coming. I hope she doesn't bring that husband of hers.(第三者の領域にあることに加えて、心理的領域に入れたくない)
彼女がやってくる。彼女があの夫を連れて来なければいいが。
He took it, said, "What's that?" and threw it away.(手に取っているが、心理的領域に入れたくない)
彼はそれを取り、「何だこれは」と言ってそれを投げ捨てた。
These inexperienced maids are always breaking dishes.(inexperienced に既に陰性感情がこもっているので、these でもよい)
この不慣れなメイドたちはいつも皿を割っている。
Take that! (人を殴るときに自分の拳であっても、心理的領域に入れていない)
これでもくらえ。
[7-1-3(電話での自分と相手の指し方)]
| 自分 | 相手 |
| 英 | this | that |
| 米 | this | this>that |
つまり、英では話し相手の実際の位置に重点を置き、米では声の聞こえて来るスピーカーに重点を置いている。
Hello. This is Mary. Is that Ruth?(英)
もしもし、メアリーですが、ルースさんですか。
"Hello? Is this Tracy Whitner?" "Who is this?"(米)
「もしもし、トレーシー・フォイットナーさんですか」「どなたですか」
[7-1-4(物語で)]初出のものに this を用いることがある。以下は後述するテキスト内照応(順行照応)の this でもあるが、作者は登場人物に対する親しみを読者にもってもらおうとしている。
I was walking along the street when this girl came up to me.
私が通りを歩いていると、これからお話しする女の子が近づいてきました。
[7-2(テキスト内照応の this, these, that, those)]名詞句はもちろん、動詞句、形容詞句、節、文を指しえる。
I knew there was a snake in the room, but that was not what worried me.(節 there was a snake in the room を指す)
部屋の中に蛇がいたのを知っていたが、それは私が悩んでいることではなかった。
"You are awfully strong." "I am that."(形容詞句 awfully strongを指す)
「君は凄く強い」「そうだよ」
[7-2-1(会話で)]会話で自分の言ったことの全体または部分は this で、相手の言ったことの全体またが部分は that で指示する。
"There seems to have been a error in my calculation. This is what I am confirming."
「私の計算には間違いがいくつかあったようだ。それを今、確かめているところだ」
"There seems to have been a error in your calculation." "Yes, that's what I am confirming."
「君の計算には間違いがあったようだ」「うん。それを今、確かめているところだ」
[7-2-2(逆行照応と順行照応)]thisは逆行照応と順行照応がありえる。thatは逆行照応のみ。
He abhorred fanaticism. In this he truly mirrored the spirit of Bismark's era.(逆行照応)
彼は熱狂を嫌悪していた。この点で、彼は真にビスマルクの時代の精神を反映していた。
And this I warn you: take no hand or part in negotiating with him.(順行照応)
そしてこのことを警告する。彼との交渉に一切係るな。
[7-2-3(名詞句の反復を避ける that, those )]前出の名詞句を指し代用し、the+前出の名詞句の意味になる。of - などの前置詞句, 関係代名詞節などの後方からの修飾語句を伴い、限定されたものになる。可算名詞単数形または不可算名詞は that で受け、可算名詞複数形は those で受ける。前出の名詞句は限定されたものでなく the が付いていなくてもよい。
The area of the USA is larger than that (= the area) of Brazil.
アメリカ合衆国の面積はブラジルのそれより大きい。
The finest wines are those (= the wines) from France.( wine は通常、不可算名詞だが、種類を指すときは複数形になりえる)
最高のワインはフランス産のそれらだ。
A fence divided his garden from that (= the garden) of the next house.
柵が彼の庭と隣の家の庭を仕切っていた。
[7-2-3-1( the+名詞の代用となる that, those のうち that は人を代用できない)] those は人を代用できる。
The blond girl I saw was older than /the one/×that/ you were dancing with.
私が見たブロンドの女の子は君がダンスしていた女の子より年上だった。
The blond girl I saw was older than those (/who/whom/that/) you were talking to.
私が見たブロンドの女の子は君が話していた女の子たちより年上だった。
[7-2-4(前の節の反復を避ける that)]これは省略できる。
I must consult him, and (that) at once.
彼に相談しなければならない。それもすぐに。
[7(指示代名詞)-3(例外的意味用法)]
[7-3-1( those+修飾語句)] those+修飾語句で、前出の名詞句ではなく、一般の「~の人々」を指すことがある。
Be kind to those around you.
周りの人々に優しくしなさい。
There are those who believe it, though others are skeptical.(限定された人ではなく一般の人なので There be S 構文のSになりえる)
それを信じる人もいれば懐疑的な人もいる。
[7-3-2(関係代名詞と相関的に用いる that, those )]これは what と等しく、限定されたものを指したり名詞句の代用をするのではなく、「一般の~のもの」を指す。that which, those which は物について用いるが、古風であり、what を用いるのが普通である。that who はない。those whoはあり、よく用いられ、一般の「~の人々」を指す。
/That which/what/ he told me to do I did.(OSVの形になっている。目的語の文頭移動である)=
I did /that which/what/ he told me to do.
彼に言われたことを私はしました。
He had that in his eyes which forbade further trifling.
彼の目にはそれ以上いいかげんにあしらうことを許さないものがあった。
Unfortunately, those who work hard do not always succeed.
残念なことだが、一生懸命働く人が常に成功するとは限らない。
[7-3-3(関係代名詞と相関的に用いる形容詞的用法の that, those )]形容詞的用法の that, those が関係代名詞と相関的に用いられ、上と同様に「一般の~のもの」を指すことがある。この場合も /that/those/ 名詞 which は物を指し、that 名詞 who はない。those 名詞 who は人を指し、「一般の~の人々」を指す。
I keep only those books at hand which I want to read again.
私はもう一度読みたい本だけ手元に置いておく。
The future of a nation depends upon those young people who are sound in mind and body.
国の未来は心身ともに健全な若者にかかっている。
[7-3-4(/this/that/で/後者/前者/)]古語である。
Health is above wealth, for this cannot give so much happiness as that.
健康は富に勝る。何故なら、後者は前者ほどの幸せをもたらさないから。
[7-3-5(副詞の this, that )] は so または such (a) と等しい。
"The table's about this (= so) high and this (= so) wide," she showed with her arms stretched.=
"The table's of this (= such a ) hight and this (= such a) width," she showed with her arms stretched.
「そのテーブルは高さも幅もこんなにある」と彼女は腕を広げて示した。
[7-3-5(副詞の this, that )-1(疑問文、否定文で)]= not so 「あまりない」を表す。
He isn't (all) that rich.
彼はあまり裕福ではない。
[7-3-5(副詞の this, that )-2(接続詞 that と相関する this, that)]=so, such (a)。これは古語または方言である。
I'm that (= so) hungry (that) I could eat a dog.
私は空腹で犬も食えそうだ。
He blushed to that (= such a) degree that I felt quite shy.
彼がひどく赤面したので、私も恥ずかしくなった。
[7-4(慣用句)]
[7-4-1( this and that )]「あれこれ」「いろいろ」。
He went to /this doctor and that/this and that doctor/.
彼はいろんな医者に診てもらった。
[7-4-2(慣用的に that を用いることが定着している表現)]
..., that is (to say), .... すなわち、つまり
That is that. 言いたいのはそれだけだ。
That is it. (最善策などは)ああ、それだ。
など多数ある。
[8] one
[8( one )]以下のように名詞句の代用をする。物も人も代用する。以下の形が可能である。名詞句の中で、one が先頭に来るときは不定冠詞も定冠詞も付かない。one が先頭に来ないとき、不定冠詞(a)は省略できる。
one 単独 → a+可算名詞の代用
one+後位修飾語 → a+可算名詞の代用
前位修飾語+one(+後位修飾語) → a+可算名詞の代用
a+前位修飾語+one(+後位修飾語) →可算名詞の代用
the+前位修飾語+one(+後位修飾語) →可算名詞の代用
ones 単独 → 可算名詞複数形の代用
ones+後位修飾語 → 可算名詞複数形の代用
前位修飾語+ones(+後位修飾語) → 可算名詞複数形の代用
the+ones+後位修飾語 → 可算名詞複数形の代用
the+前位修飾語+ones(+後位修飾語) →可算名詞複数形の代用
I've lost my pen, so I must buy /one (= a pen)/×it/.
ペンをなくしたので、買わなければならない。
"I've lost my pen." "Here /is one (= a pen)/it is/."
「私はペンをなくした」「ここに/別のがあるよ/それがあるよ/」
上の違いに注意。it を用いるとまさしくなくしたペンがあるのである。また、one では VSの倒置が起こるが、it を含む人称代名詞、指示代名詞では倒置が起こらない。
I am looking for a flat. I'd like one (= a garden) with a garden.(後位修飾語付き)
フラットを探している。庭付きがいいね。
I'd like (a) small one with a garden.(前位修飾語付き)
庭付きの小さいのがいいね。
He was a bachelor and was likely to remain one.(人を代用)
彼は独り者で、独り者で通しそうだった。
The year has been one of political unrest.(後位修飾語付き)
その年は政治不安の年だった。
These are our best shirts. Which /one/ones/ would you like to try on?(前位修飾語付きだが、疑問形容詞、関係形容詞が付く場合は冠詞は付けない)
これは当店最高級のシャツでございます. どれかお召しになってみますか。
[8-1( one の前位修飾語として、some, any, every, no, neither も)]可能である。ただし、no one は none となる。また、some, any, neither は代名詞でもあるので、one は省略可能である。また、それらとは別に someone, anyone, everyone, no one はそれら自体代名詞になっている。ただし、それらは人のみを代用する。
/Neither (one)/None/ of them said anything for nearly a minute.(neither は them が二人の場合、none は them が三人以上の場合)
一分近く、彼らの/どちらも/誰も/何も言わなかった。
[8-2( one を用いることができない場合)]
[8( one )-2-1(不可算名詞は代用しない)]
Give me some water, please. Tap /water/×one/ will do.
水を下さい。水道水でいいです。
[8( one )-2-2(所有格の後では用いられない)]独立所有格を用いる。ただし、所有格+形容詞+oneは可能である。
My house is smaller than his (×one).
私の家は彼の家より小さい。
My house is smaller than his expensive one.
私の家は彼の高価な家より小さい。
[8( one )-2-3(基数詞の後では用いられない)]ただし、基数詞+形容詞+one は可能。
He has three rabbits and I have only two (×ones).
彼はウサギを三匹かっているが、私は二匹だけかっている。
[8( one )-2-4( pair の代わりはできない)]。
This pair of shoes /is/×are/ not mine. Mine is that new /pair/×one/.
この靴は私のではありません。私のはあの新しい靴です。
[8( one )-3(数詞としての one )]数詞としての one は上の代名詞の one とは異なり、two, three... と文法的に等価である。
/One/Two/ of the girls /was/were/ late.
それらの女の子のうち/一人/二人/が遅刻した。
/He/They/ /is/are/ /one/two/ of us.
/彼/彼ら/は仲間だ。
[8( one )-4( 総称 )]前述のとおり、一般の人を指す総称としての one もあるが、格式体である。
[9] so, such, thus, the same
[9-1( so )] so は基本的に副詞だが、代名詞のような機能ももつ。結局、叙述名詞句( fool など)、形容詞句、副詞句、節を代用する。
Prices at present are reasonably stable, and will probably remain so.(形容詞句)
現在の物価はほどよく安定している、今後もたぶんそうだろう。
If he's a criminal, it's his parents who have made him so.(叙述名詞句)
彼が犯罪者だとしたら彼をそうしたのは両親だ。
She searched the big room very carefully and the small one less so.(副詞句)
彼女は大きな部屋を注意深く捜したが、小さい部屋はさほど注意深く探さなかった。
"Has he failed?" /"I think so."/"I think not."/(節)
「彼は失敗したのか。」/「そう思う。」/「そうでないと思う。」/
"Are you really coming?" "I told you so."(節)
「本当に来るんですか。」「そう言ったでしょう。」
"Will he succeed? " "I hope so." "I'm afraid not."(節)
「彼は成功するだろうか。」「そう思う。」「成功しないと思う。」
[9-1( so )-1( that節の代用)]上の三つの例文のように so が that節を代用することはよくある。否定の節をどう代用するかは動詞によって決まっている。
[9-1( so )-1( that節の代用)-1(肯定の節を so が代用し、否定の節を not または not - so が代用する動詞)]think, suppose, be afraid, appear, assume, expect, fancy, imagine, presume, seem, tell, understand
"Would Ukraine succeed in countering Russian invasion?" "/I think so/I think not=I don't think so/."
「ウクライナはロシアの侵攻への反撃に成功するのだろうか」「/成功すると思う/成功しないと思う/」
[9-1( so )-1( that節の代用)-2(肯定の節を so が代用し、否定の節を not が代用し、not -so が代用しない動詞)]hope。
"Is it going to rain?" "/I hope not/×I don't hope so/."
「雨になりそうですか。」「降らなければいいんだが」
[9-1( so )-1( that節の代用)-3(肯定の節を so が代用し、否定の節を not - so が代用し、not が代用しない動詞)]claim, declare, say, state, tell などの伝達動詞。
"Did she tell you that she was coming to the party?"
/"Yes. She told me so."/"No. She didn't told me so."/×No. She told me not./
「彼女はパーティーに来ると言いましたか」
/「はい、そういいました」/「いいえそうは言いませんでした。」/
[9-1( so )-4(節を so が代用し、so を文頭に回すことがあり)]そのとき主語が名詞なら倒置を起こし、代名詞なら倒置を起こさない動詞。
appear, seem, say
"Is there life on Mars?" "So it /appears/seems/."
「火星には生物がいますか。」「そのようです。」
"She is a pretty girl." "So say all my friends."
「彼女はかわいい。」「友達もみんなそう言っている。」
[9-1( so )-5(節を so が代用し、so を必ず文頭に回し)]倒置については同上である動詞。see, hear, gather, notice
"Is it raining outside?" "So I see."
「外は雨ですか。」「そのようです。」
[9-1( so )-6(節を代用する so と it の違い)]節の内容が真であるという態度を明確にするには it を用いる。
She asserts that he is innocent, and I assert it too.
彼女は彼が無実だと主張している、私もそうだと主張する。
[9-1-7( so S V と so V S の違い)]前者は「そのとおり」、後者は「~もそうする」。
"Sally is a nice girl." "So she is."
「サリーはいい子だ」「そのとおり」
"I'm hungry." "So am I."
「お腹が空いた」「私もだ」
[9-1-8(副詞 so )]上の代名詞のような機能をする so と異なり、明らかな副詞 so は程度が大きいことを表す。
[9-1-8(副詞 so )-1( so+形容詞+不定冠詞(a)+名詞)] so が形容詞を修飾して形容詞句を構成し、その形容詞句がさらに名詞を修飾することがある。その場合は、so+形容詞+不定冠詞(a)+名詞の語順になる。だが、これは古語である。現代では such+不定冠詞(a)+形容詞+名詞を用いる。
It was so mysterious a night.→
It was such a mysterious night.
それはすごく神秘的な夜だった。
[9-1-8(副詞 so )-2(/so - that/so - as to不定詞/)]
の形で「~なほど~」「~なので~」という程度、結果を表すことがある。この so は順行照応とも言える。
[9-2( such )] such について。such が代用するものは、名詞句だけでなく形容詞句、副詞句、節、文である。代名詞、名詞修飾語、副詞としても機能する。
I may have offended, but such was not my intention.(代名詞として機能、節を代用する)
怒らせたかもしれないが、そのようなことは私の意図するところではなかった。
He is a friend and I treat him as such.(代名詞として機能、名詞句を代用)
彼は友人であり、私は友人として扱う。
He rearranged the letters of the correspondance such that it looked senseless.(副詞として機能、such - that で相関接続詞、順行照応)
彼は書簡の文字を並べ変えて、意味が読めないようにした。
[9-2( such )-1(名詞修飾語として so と異なり、可算名詞単数形だけでなく可算名詞複数形も不可算名詞も修飾できる)]
Don't be in such a hurry.(可算名詞単数形)
そんなに急ぐな。
The girls were escorted by some such modest attendants that they stood out also in the flash of the media.(可算名詞複数形)
控え目な随行員に付き添われたので、それらの女の子はマスコミのフラッシュを浴びる中でも引き立った。
He cannot come too often, he gives such pleasure.(不可算名詞)
彼なら何回来てもいい。それほど楽しいんだ。
[9-2-2( such と併用可能な代名詞、不定数詞)] some, other, no, many, a few, few などが併用可能で、それらは such の前に来る。それらが付くと冠詞はつかない。
There is no such thing as a miracle. What seems so is no more than an accident.
奇跡なんて存在しない。そのように見えるものは偶然に過ぎない。
"There was no such operation as the Soviets and the Cubans completely collaborated on," said Fidel Castro.
「ソビエト人とキューバ人が完全に協調するような作戦は一つもなかった」とフィデロ・カストロは言った。
There was no such thing as a "peaceful population". They were all guerrilla fighters.
「平和な住民」のようなものは存在しなかった。彼らは皆、ゲリラ戦士だった。
There are many such things as we call "peaceful coexistence".
「平和的共存」と呼ばれるようなものはたくさんある。
[9-2( such )-2-1(形容詞の最上級との併用も可能)]形容詞の最上級との併用も可能であり、最上級は前に来る。
Some creeds insist that people should believe in only one of them. The most fanatical /such creed/of such creeds/ is fascism.
信条のうちの一つだけを人は信じるべきだと主張する信条がいくつかある。そのような信条のうち最も狂信的なものがファシズムだ。
[9-2-3( such A as B )] as と相関して、such A as B の形になることがよくある。
Such poets as Keats are rare.
キーツのような詩人はまれだ。
You may use my car, such as it is.
こんなものだが、ぼくの車を使ってもいいよ。
[9-2-3-1( A such as B )]非文法的だが、慣用的に、such と as がくっついて、A such as B となることがある。現代では like のほうがよく使われる。
China is in the competition with U.S. also to produce next-generation technologies /such as/like/ artificial intelligence.
中国は人工知能のような次世代技術を生み出すうえでも合衆国と競争している。
[9-2-4( such - /as to不定詞/that節/)] as to不定詞、that 節と相関することがある。
His indifference is such as to make one despair.
彼の無関心は人を絶望させるほどのものだ。
His behavior was such/Such was his behavior/ that everyone disliked him.
彼の振る舞いはひどかったので、皆が彼を嫌った。
He rearranged the letters of the correspondance such that it looked senseless.
彼は書簡の文字を並べ変えて、意味が読めないようにした。
[9-3( thus )] thus が代用するものは、副詞句のみであ。
He sold his car and used the money thus obtained to fly to Rio.
彼は車を売って,それで得たお金をリオデジャネイロへの飛行機代にした。
[9-4( the same )] the same が代用するのは、名詞句、形容詞句、副詞句、節である。
"Can I have a cup of black coffee with sugar?" "Give me the same."(名詞句)
「砂糖入りのブラックコーヒーをもらえますか」「私にも同じものをください」
They all started shouting. So I did the same.(名詞句)
皆、叫び始めた。そこで、私も同じようにした。
The soup smelled delicious, and the turkey smelled the same.(形容詞句)
スープがおいしそうな臭いがした。七面鳥もおいしそうな臭いがした。
[10] do so, do it, do this, do that, do the same
[10( do so, do it, do this, do that, do the same )]それらは意図的行為に用いられるので、think, own, like, rememberなどの状態動詞や自発的な動作動詞には用いられない。前の動詞句の全体または部分を代用する。
They think he's wrong, and I do (×so) too.
彼らは彼が間違っていると思っている。私もそうだ。
He ate beans with a fork, and she did so, too.(前の動詞句の全体 ate beans with a fork を代用)
彼はフォークで豆を食べ、彼女もそうした。
前の文が ... and so did she.となると、この did は助動詞である。
He ate beans with a fork, and she did so with a spoon.(前の動詞句の部分 eat beans を代用)
彼はフォークで豆を食べ、彼女はスプーンでそうした。
[10-2( do so と do it の違い )]。同一の行為では do it が好まれ、同様の行為では do so が好まれる。
He is painting the house. I'm told he does it every four years.
彼が家にペンキを塗っている。四年ごとにそうするんだって。
He is painting the house. I'm told this is because his neighbor did so last year.
彼が家にペンキを塗っている。それはお隣さんが去年にそうしたからだそうだ。
[10-3( do it と do thatの違い)]後者には直示性があり、感情がこもる。
Are you trying to light the stove with a match. I wouldn't do that.
マッチでストーブを着けようとしているのか。ぼくならそんなことはしない。