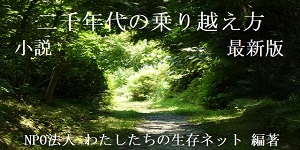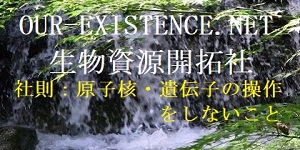COPYRIGHT(C)2000 OUR-EXISTENCE.NET ALL RIGHTS RESERVED
一歩先を行く英文法トップページ
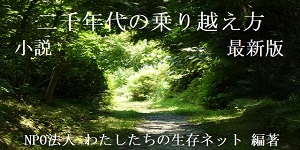
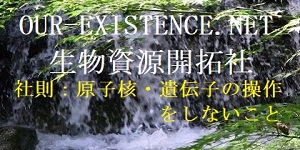
不定詞
[1]不定詞総論
[1-1(不定詞の種類、時制、態)]
まず、不定詞には原型不定詞とto不定詞がある。さらにそれぞれに、完了形、進行形、受動態がある。
| | 不定詞 | 完了形の過去分詞 | 進行形の現在分詞 | 受動態の過去分詞 |
| 原型不定詞 | History could | have | been | being | written. |
| to不定詞 | History seems | to have | been | being | written. |
歴史は書き換えられてきた/のかもしれない/ようだ/。
[1-2(能動不定詞、受動不定詞のうちどちらを用いるか)]の原則は以下のとおりである。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-1(不定詞に内在する事情)]不定詞の主語が for で示されているときで、動詞、句動詞の目的語であったものが不定詞の主語になっているときは受動不定詞を用い、それ以外では能動不定詞を用いる。
I found a book for my child to read.
子供が読む本を私は見つけた。
She proposed to them some ways for their weapons to be reduced.
彼女は彼らに兵器削減の方法をいくつか提案した。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-1-1( for は必ずしも不定詞の主語を示さない)]例を挙げる。
It is for us to find the connection.(for は「~のため」という意味の前置詞であり、形式主語 it は to find the connection のみを代替する)
その関係を見出すことが私たちの仕事だ。
It is not for me to judge you.(同上)
君を裁くのは私の役目じゃない。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-2(形容詞的用法)]で修飾されるまたは叙述される名詞句が、不定詞の主語であるときは能動不定詞を用い、不定詞の目的語である場合は受動不定詞を用いる。ただし、例外は後述する。
The people to interview are in the next room.(修飾される the people が interview の主語)
面接を担当する人々は隣の部屋に居る。
The people to be interviewed are in the next room.(修飾される the people が interview の目的語)
面接される人々は隣の部屋に居る。
These sheets are to be washed(叙述される these sheets が wash の目的語).
これらのシーツは洗濯されなければならない。
It is to be hoped that the heaven forgive him that lie.(叙述される it = that節 が hope の目的語)
願わくは天が彼のあの嘘を赦されることを。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-2(形容詞的用法)例外]ただし以下は例外
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-2(形容詞的用法)例外1]文の目的語を修飾する形容詞用法限定用法で、不定詞の主語が文の主語であるとき、[1-2-2]に反して能動不定詞を用い、不定詞の主語が文の目的語であるときは[1-2-2]の通り能動不定詞を用いる。
I have some work to do.( do の主語が文の主語 I)
わたしにはする仕事がある。
I have no one to help.( help の主語が文の主語 I)
私には助ける人がいない。
I have no one to help me.( help の主語が文の目的語 no one)
私には助けてくれる人がいない。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-2(形容詞的用法)例外2] There be S to不定詞 の文型では能動不定詞でも受動不定詞でもどちらでもよい。ただし意味が異なることがある。
There is no time to lose. = There is no time to be lost.
ぐずぐずしている時間はない。
There is nothing to see. ≠ There is nothing to be seen.
見るべきものはない。≠ 見えるものは何もない。
There's nothing to do―I'm bored.
何もすることがない―退屈した。
There's nothing to be done―we'll have to buy another one.
どうしようもない―買い替えなければならないだろう。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-2(形容詞的用法)例外3]慣用句で必ず能動不定詞を使うものがある。
Is there a house to let around here.
賃貸の家はこの辺りにありますか。
The driver was to blame for the accident.
その事故の責任は運転手にある。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-3(動詞+名詞句+to不定詞)]動詞+名詞句+to不定詞の文型で、名詞句が不定詞の主語であるとき、能動不定詞を用い、名詞句が不定詞の目的語であるときは受動不定詞を用いる。
I want you to return all these books by tomorrow.(you が return の主語)
私はあなたにこれらの本をすべて明日までに返してもらいたい。
I want all these books to be returned by tomorrow.(all these books が return の目的語)
これらの本をすべて明日までに返してもらいたい。
[1-2(能動不定詞か受動不定詞か)-4]上記の[1-2-1][1-2-2][1-2-3]以外で不定詞の主語が一般の人のときはどちらでもよい。
This story is too long to read in an hour. = This story is too long to be read in an hour.
この物語は長すぎて一時間で読めない。
[1-3(進行形不定詞)]
[1-3(進行形不定詞)-1(意味)]進行形の意味(継続、反復、切迫、一時的状態、推移、未来…など)が加わる。
He seemed to be listening to me.(継続)
彼は私の言うことに耳を傾けているように見えた。
She seemed to be dying.(切迫)
彼は死にかけているように見えた。
I suppose we ought to be going.(未来)
わたしたちはおいとましなければならないと思います。
He is believed to be living in Boston.(一時的状態)
彼は現在、ボストンに住んでいると信じられている。
He is said to be resembling his father.(推移)
彼は父親に似てきていると言われている。
[1-3-2(進行形原型不定詞)]助動詞の後で原型の進行形不定詞が現れることもある。
He may be watching TV.
彼はテレビを見ているかもしれない。
[1-4(完了進行形不定詞)]完了不定詞については後に詳述する。ここでは、完了進行形の不定詞の例文を挙げる。
He seemed to have been reading.
彼は読書をしていたように見えた。
[1-5(進行形不定詞受動態)]
History seems to be being rewritten.
歴史は書き換えられているように見える。
[1-6(動詞+to不定詞 が 動詞 and 動詞 となる)]ことがある。以下の場合で。
[1-6-1(命令文)]命令文で try to不定詞が、 try(命令法) and 動詞(命令法)となることがある。
Try and be patient.
我慢強くするよう努めなさい。
[1-6-2(助動詞の後)]助動詞の後で try が原型不定詞になるに伴って、try to不定詞が try and 原型不定詞になることがある。
You must try and be patient.
君は我慢強くするよう努めなければならない。
[1-6-3( try がto不定詞)] try がto不定詞になるとき、try to不定詞が try and 原型不定詞になることがある。
The government decided to try and tackle economic crisis.
政府は経済危機に取り組もうと決定した。
[1-6-4(/go/come/+to不定詞)]/come/go/(往来発着の動詞)+to不定詞 が、/come/go/ and 動詞となることがある。さらに and もなくなることがある。これらは略式体である。
Come and dine with me.
食事に来て。
I will go and get the phone.
私が電話を取りに行く。
[1-7(不定詞と副詞の位置関係)]
[1-7(副詞の位置)-1(中位の副詞)] not を含めて中位を占めるような副詞は、to不定詞においては to の直前に置き、原型不定詞においてはその直前におく。not について、to不定詞の否定形は not+to不定詞 である。原型不定詞の否定形は not+原型不定詞 である。
She ran away so as not to meet him.
彼女は彼に会わないように逃げた。
He tried not to think about it.(not は to不定詞だけを否定する)
彼はそのことを考えないようにした。(考えないように努力した)
He did not try to think about it.(not は文全体を否定する)
彼はそのことを考えようとしなかった(考えることを怠った)。
You are silly not to have locked your car.(not は to不定詞を否定する)
車に鍵を掛けなかったとは君は馬鹿だ。
You are not silly to have locked your car.(not は文全体を否定する)
車に鍵を掛けたとは君は馬鹿ではない。
[1-7(副詞の位置)-2(中位の副詞以外)]中位の副詞以外について、to不定詞の直前においても to と動詞の間に置いても to不定詞の末尾においてもよい。そうしなければ誤解が生じる場合は to と動詞の間に置く。
以下の文では誤解が生じないので次の三つの位置が可能である。
He was wrong to leave the country suddenly.
He was wrong suddenly to leave the country.
He was wrong to suddenly leave the country.
彼が突然、国を去ったのは間違いだった。
以下の文では誤解が生じえるので to と動詞の間に置く。
He failed to entirely understand it.
彼はそれを完全には理解できなかった。
She urged him to simply accept it.
彼女は彼にそれをあっさり受け入れるよう促した。
[1-7(副詞の位置)-3(複数の不定詞があるとき)]等位接続詞で不定詞を繋ぐ場合は、to不定詞 and to不定詞としても、to不定詞 and 原型不定詞としてもよい。to不定詞 and 原型不定詞とする場合、not を含めて中位の副詞が to の後に来ることがある。
When one discusses Europe, it is important to not just talk about the individual countries but also think about the European Union's role.
ヨーロッパを論じるとき、個々の国について語るだけでなくヨーロッパ連合の役割を考えることは重要である。
[1-8(不定詞の名詞的用法と動名詞との違い)]一般に不定詞は未来志向的であり、動名詞は事実指向的である。その違いは不定詞と動名詞を目的語にとりえる remember, forget で明確になる。
Please /don't forget/remember/ to post the letter tomorrow morning.
明日の朝、手紙を出すのを忘れないでください。
He /remembers/forgets/ posting the letter this morning.
彼は今朝、手紙を投函したことを/覚えて/忘れて/いる。
The girl was afraid to go out alone at night.
その女の子は(そのときは)怖がって夜に一人で外出しようとしなかった。
The girl was afraid of going out alone at night.
その女の子は(一般に)夜に一人で外出することを恐がっていた。
[2]不定詞の主語
[2(不定詞の主語)]は基本的に不定詞の前で for+不定詞の主語 の形で示す。この for は前置詞ではなく、不定詞の主語を示す記号のようなものである。それは to不定詞の to が前置詞でないのと同様である。
It's dangerous for children to swim in this river.
この川で子供が泳ぐのは危険だ。
[2-1(主語を表示する必要がない場合)] to不定詞の主語は必ずしも示す必要がない。また、文の中に主語が既に現れている場合がある。to不定詞の主語を表す必要がない場合または既に現れている場合は以下の通りである。
①不定詞の主語が一般の人々のとき。不定詞の主語を表す必要なし。
②文脈から不定詞の主語が明白なとき。不定詞の主語を表す必要なし。
③不定詞の主語が文の主語と同一のとき、既に現れている。
④不定詞がSVO(sc)文型の小節の中の小補語(c)のとき、小主語(s)として既に現れている。
⑤不定詞がSVOC文型のCであるとき。Oとして既に現れている。
⑥ it is 形容詞 of句 to不定詞の構文において、of の目的語として既に現れている。これについては後述する。
It's dangerous (for /us/you/) to swim in this river.①
この川で泳ぐのは危険だ。
It was too cold (for me) to go out.②
寒すぎて外出できない。
I want to go out.③
私は外出したい。
I have some letters to write.③
私は書くべき手紙がある。
He promised me never to show up late again.③
彼は私に二度と遅れませんと約束した。
I want you to read this.④
私はあなたにこれを読んでほしい。
I believe the story to be true.④
私はその話が本当だと信じている。
We urge you to vote against the bill.⑤
ぜひその法案に反対票を投じましょう。
Government troops have forced the rebels to surrender.⑤
政府軍は反乱軍を降伏させた。
[2-1-1(形容詞+of句+不定詞)]形容詞+of句+不定詞の形になるときは、ofが不定詞の主語を示すように見える。だが、実際はこの of は、形容詞が表す属性が、主語(形式主語が立つことがあるが)になっている不定詞が表す動作や状態に属することを示す of である。いずれにしても、不定詞の主語が of の目的語として既に現れている。ofの目的語を文の主語にすることが可能であり、そのときは形容詞が主語の属性を表し、不定詞が判断の根拠を示す。
It is kind of you to come.=
You are kind to come.
来てくれてありがとう。
It was /impudent/saucy/ of you to say that to your mother.=
You were /impudent/saucy/ to say that to your mother.
あんなことをお母さんに言うとは、あなたは生意気だ。
それらに対して、以下では不定詞の主語を for が示している。
It is difficult for her to solve the problem.=
×She is difficult to solve the problem.(不定詞の主語を文の主語にすることができない)
〇The problem is difficult for her to solve.(不定詞の目的語を文の主語にすることはできる)
彼女がその問題を解くことは不可能だ。
[2-2([2-1]を除いて、to不定詞の主語は for で示す)]この for は前置詞ではなく、その後の語句が不定詞の主語であることを示す記号のようなものである。不定詞の主語を示す for が使われるのは以下の [2-2-1]~[2-2-6]の不定詞の用法においてである。
[2-2-1(名詞的用法、不定詞が文の主語になる]不定詞の代わりに形式主語 it を置くことが多い。
It is unusual for her door to be open.
彼女の家のドアが開いているのは異常だ。
It is impossible for me to persuade her to do it.
私が彼女にそれをするよう説得するのは不可能だ。
[2-2-2(名詞的用法、不定詞が主格補語になる)]
His idea is for us to travel together.
彼の考えは私たちが一緒に旅をしようというものだ。
[2-2-3(名詞的用法、不定詞が欲求動詞の目的語になる)]不定詞が欲求動詞(want, like, intend, etc)の目的語になっているとき、米では for で不定詞の主語を示すことがある。英でも、動詞の後に副詞が挿入されると for が現れる。br>
I want her to be happy.(英米)
I want for her to be happy.(米でときに)
I want very much for her to be happy.(英米)
[2-2-4(名詞的用法、不定詞がSVOC文型のOまたはSVO(sc)文型の小節の中の小主語になる)]形式主語 it を用いる。
I thought it strange for her to be out so late.
彼女がこんなに遅くに外出しているのは奇妙だと私は思った。
He made it very difficult for us to refuse.
彼は私たちが断るのを非常に困難にした。
[2-2-5(形容詞的用法で)]
It's time for the children to go to bed.
子供たちが寝るべき時間です。
There's nothing for us to eat.
私たちが食べるものがない。
[2-2-6(副詞的用法で)]
I am anxious for him to meet her.
彼が彼女に会うことを私は切望している。
I'd be delighted for him to come.
彼が来てくれれば私はうれしい。
This book is easy enough for you to understand.
この本は君にも理解できるほど易しい。
This box is too heavy for you to lift.
この箱は重すぎて君には持ち上げられない。
[2-3(不定詞においても、there be S 構文の there は主語として扱われる)]。
It is unusual for there to be so many people there.(一番目の there が there be S 構文の there である。二番目の threre は単なる副詞である)
そこにそんなにたくさんの人々がいるのは珍しい。
[2-4( for 名詞句 to不定詞の形になっているからと言って必ずしも for は不定詞の主語を示さない)]
It is for us to find the connection.(for は「~のため」という意味の前置詞である)
その関係を見出すことが私たちの仕事だ。
It is not for me to judge you.(同上)
君を裁くのは私の役目じゃない。
[3]名詞的用法
[3(不定詞の名詞的用法)]文、節の中で不定詞が文の主語、動詞の目的語、主語の補語(主格補語)、目的語の補語(目的格補語)、SVO(sc)文型の小節の中の小主語または小補語として機能する。それが不定詞の名詞的用法である。動名詞にも名詞的用法があるが、不定詞は未来志向的であり、動名詞は事実志向的である。
[3-1(主語として機能する名詞的用法)]主語として機能する。形式主語 it を主語の位置において、不定詞は文末に置かれることが多い。
[3-2(主格補語として機能する名詞的用法)]主格補語として機能する。aim, idea, intention, purpose, proposal, plan, ambition, desire, hope, wish など目的、願望、計画…などを表す名詞を主語とすることが多い。
My only aim is to win the race.
私の唯一の目的はこのレースに勝つことだ。
[3-2-1(主語と補語の逆転)]補語を主語にしても意味が大きく変わらない場合は、そうすることが多く、形式主語 it を用いることが多い。
It is my only aim to win the race.
私の唯一の目的はこのレースに勝つことだ。
[3-2-2(原型不定詞になる場合)]次のような場合、to不定詞の to が落ちて、原型不定詞になることが多い。
[3-2-2-1(主語が do を含む)]と、to不定詞の to が落ちるが普通である。
All a novelist can do today is warn.
今日、小説家にできることは警告することだけだ。
All we have to do is look for proof.
俺たちは証拠を探していればいいんだ。
[3-2-2-1-1(昔の英語では to が落ちないことが多かった)]
The best thing I can do is to go to bed.
最善の策は寝ることだ。
[3-2-2(原型不定詞になる場合)-2(上記だけでなく、一般に話し言葉で)] to が落ちることがある。特に問いに対する答えで。
What are you trying to do to me―pull some sort of trick on me!
お前は俺に何をしようとしているんだ―ペテンにでもかけようというのか。
What shall we do after super? Go to a theatre?
夕飯が済んだらどこへ行こうか。劇場にでも行くか。
[3-2-3(主語も補語もto不定詞)]になると、二つの行為の同一性を示すのではなく、「~すればすぐに~する」の意味になることが多い。そのような文では主語と補語を逆にできない。この場合、主語においても補語においても to を落とすことができない。
To see her is to love her.
彼女を見るとすぐに愛するようになる。
×To love her is to see her.
[3-3(目的語として機能する名詞的用法)]
[3-3-1(SVO文型のO)]として機能する。to不定詞は、agree, aim, choose, decide, deserve, expect, hope, like, long, mean, offer, plan, prefer, premise, refuse, try, want, wish …など目的、願望、計画…などを表す未来志向の動詞の目的語になる。
I decided to study law.
私は法律を勉強することに決めた。
Such a man doesn't deserve to live!
そんなやつは生きるに値しない。
[3-3-1-1(受動態不可)] Oがto不定詞になったSVO文型において、to不定詞を主語にした受動態は不可である。
He decided to go.→
×To go was decided by him.
×It is decided by him to go.
彼は行くと決めた。
[3-3-2(SVOC文型のO)] to不定詞がSVOC文型のOまたはSVO(sc)文型の小節の中の小主語になっているとき。think, find, feel などの認識動詞においてが多い。形式主語 it を置くことが必須である。
I think it better not to tell it to her.
私はそれを彼女に言わないほうがいいと思う。
He found it easy to learn German.
彼はドイツ語を学ぶのはやさしいということが分かった。
I feel it my duty to help him.
私は彼を助けるのは私の義務だと感じる。
[3-4(SVO(sc)文型の小節の中の小補語として機能する名詞的用法)]不定詞が従来のSVOC文型のCになっているように見えるが、実際はSVO(sc)文型の小節の中の小補語になっている文型がある。to不定詞の主語を示すのに for を用いることがあるVと、for を用いないVがある。また、原型不定詞を用いるVがある。
[3-4-1(for を用いることがあるV)]欲求動詞(want型の動詞)である。米で for を用いることがある。米でも英でも very much などの程度の副詞が欲求動詞と不定詞の間に入ると、for を用いる。
I want (for) you to do it.(米)
私はあなたにそれをして欲しい。
I want very much for you to do it.(英米)
私はあなたにそれを是非、して欲しい。
[3-4-2( for を用いず、to不定詞を用いるV)]。使役動詞の一部、認識動詞、自動詞+前置詞である。
Her behavior caused me to laugh.(使役動詞)
彼女のしぐさに私は笑ってしまった。
He believes himself to be a good cook.(認識動詞)
彼は自分が料理がうまいと信じている。
Can I /rely on/count on/ you to help me?(自動詞+前置詞)
私は君が助けてくれることを当てにしていいのかな。
We waited for the bus to come.
私たちはバスが来るのを待った。(自動詞+前置詞)
[3-4-3(原型不定詞を用いることがあるV)]原型不定詞を用いることがあるV。使役動詞の一部と知覚動詞である。
I had the mist come.(使役動詞、受動)
霧が立ちこめてきた。
He saw her enter the house.(知覚動詞)
彼は彼女がその家に入るのを見た。
[3-4-3-1(受動態になるとto不定詞になる)]
She was seen to enter the house by him.=
She was seen by him to enter the house.
[3-5(SVOC文型のCとして機能する名詞的用法)] to不定詞が本物のSVOC文型のCになっているとき。force, compel, urge, oblige, provoke などの動詞で。
He forced her to do it.
彼は彼女にそれをさせた。
Oppression provoked the people to rebel.
圧政に怒って民衆は反乱を起こした。
[3-6(SVIODO文型のDOとして機能する名詞的用法)] to不定詞がSVIO(間接目的語)DO(直接目的語)文型のDOになっているとき。
I advised her to wait and see.
私は彼女に様子を見るよう助言した。
I told her to see a doctor.
私は彼女に医者に診てもらうよう言った。
He promised me never to show up late again.
彼は私に二度と遅れませんと約束した。
[3(名詞的用法)-7(形式主語・目的語 it が変わりをする場合)]
[3-7-1( to不定詞が主語になる文では、形式主語 it を用いることが多い)]
It is nice to be sitting here with you.
ここであなたと一緒に座っているのは素敵です。
[3-7-1-1( to不定詞が補語になる文において)] to不定詞を主語にしても意味が大きく変わらない場合は、そうすることが多く、形式主語 it を用いることが多い。
My only aim is to win the race.→
It is my only aim to win the race.
私の唯一の目的はこのレースに勝つことだ。
[3-7-2( to不定詞がSVOCの文型のOになっている場合)]とSVO(sc)文型の小節の中の小主語になっているときは it を用いることが必須である。
〇I feel it my duty to help him
×I feel to help him my duty.
.
私は彼を助けるのは私の義務だと思う。
[3-8(慣用的表現)]
[3-8-1(主語も補語もto不定詞)]である文の意味。同一性から発展して、「~すれば必ずすぐに~する」。逆にはできない。
To see her is to love her.
彼女を見れば愛するようになる。
[3-8-2(動詞としての please の後にto不定詞が来る)]構文があるが、古語または方言である。
Please not to forget the key.→
Please don't forget the key.
鍵を忘れないでください。
[4]SV+(for)名詞句+(to)不定詞の形をとる文型について
[4]従来の文法では、SV+(for)名詞句+to不定詞の文型をすべて、(for)名詞句を O(目的語)、不定詞を C(目的格補語)として、SVOC文型ととらえてきた。現在は、それらの(for)名詞句+to不定詞の多くは、(for)不定詞の主語+to不定詞ととらえられ、一つの小節(sc)ととらえられ、一つの目的語としてとらえている。つまり、SV+(for)名詞句+(to)不定詞の文型の多くは、SVO(sc)文型ととらえられている。だが、本物のSVOC文型ととられられるものも残っている。結局、動詞+(for)名詞句+(to)不定詞の形をとる文型は以下の型に分類できる。
[SVO(sc)文型]
①want(欲求動詞)型
want, like, hate, etc
②think(認識動詞)型
think, believe, know, find, etc.
③get(使役動詞)型
get, cause, bring, etc
make, have, let では原型不定詞になるが、不定詞の主語を文の主語にした受動態を作れ、その場合は to不定詞になる。
④see(知覚動詞)型
see, hear, feel, etc
原型不定詞になるが、不定詞の主語を文の主語にした受動態を作れ、その場合は to不定詞になる。
⑤rely upon(自動詞+前置詞)型
rely on, count on, long for, etc.
[本物のSVOC文型]
⑥force(SVOC)型
force, provoke, urge, etc.
[4-1(want(欲求動詞)型]人、物に係る情動を表す。不定詞の主語を示すのに for を用いることがある。
I hate girls to smoke.
私は女の子が煙草を吸うのが嫌いだ。
私は女の子が嫌いなのではなく、女の子が煙草を吸うという習慣的動作が嫌いなのである。だから、不定詞の主語+to不定詞を一つの小さな節ととらえ動詞の目的語とするとらえ方には納得が行くだろう。
[4-1-1( for の有無)]米で want型で to不定詞の主語に for が付くことがある。英でも動詞とto不定詞の間に very much などの副詞句が挿入されると for が付く。
I want him to come early.(米英)=
I want for him to come early.(米)
私は彼に早く来てほしい。
I want very much for you to be happy.(米英)
私はあなたが幸せになることを切望しています。
[4-1-2( hope )] hope は want と意味的に似ているが、hope+不定詞の主語+to不定詞の形では用いられない。hope+to不定詞、hope+for+不定詞の主語+to不定詞、hope+for+名詞・動名詞、hope+that節は可能である。
〇I hope to come.
私は来たい。
〇I hope that you will come.
×I hope you to come.
〇I hope for you to come.
〇I hope for /your/you/ coming.(/your(所有格)/you(目的格)/は動名詞 coming の主語である)
私はあなたに来て欲しい。
[4-2(think(認識動詞)型)] think(認識動詞)型。人、物に係る認識を表す。それも一時的な認識ではなく、持続的反復的な認識を表し、この型の動詞は状態動詞であり、通常、進行形にならない。不定詞はほとんどが to be の形をとり、to be は省略されうる。だが、不定詞またはその省略は格式体であり、that節を用いるほうが普通である。
I thought her (to be) a genius.→
I thought that she was a genius.
私は彼女は天才だと思っていた。
[4-3(get(使役動詞)型)] get(使役動詞)型。get, cause, bring, leave, etc
make, have, let では原型不定詞になる。
He /got his wife to/had his wife/ mend his shirt.
彼は妻にシャツを繕ってもらった。
I couldn't bring myself to study hard.
私は一生懸命勉強する気にはなれなかった。
Leave him to take care of himself.
彼には自分のことは自分でさせなさい。
[4-3-1(受動態)] make については不定詞の主語を文の主語にした受動態を作れ、その場合は to不定詞になる。ただし、人間の意志によって強制されえる動作に限る。
They made him account for the accident.→
He was made to accoung for the accident.
彼はその事故の原因の説明をさせられた。
The accident made him die.(人間の意志によって強制されえない)→
×He was made to die by the accident.
事故が彼の命を奪った。
[4-4(see(知覚動詞)型)] see(知覚動詞)型。see, hear, feel, etc. 原型不定詞になるが、不定詞の主語を文の主語にした受動態を作れ、その場合は to不定詞になる。
They saw him steal into the house.→
He was seen to steal into the house.
彼はその家に忍び込むところを見られた。
[4-5(rely on(自動詞+前置詞)型)] rely on型。自動詞+前置詞+不定詞の主語+to不定詞の形をとる。これもSVO(sc)文型ととらえることができる。
Can I count on you to help me.
君が助けてくれるのを当てにしていいですか。
I longed for her to phone.
私は彼女が電話してくれるのを待ち焦がれた。
We waited for the bus to come.
私たちはバスが来るのを待った。
I will arrange for a car to be there.
車がそこに手配しましょう。
He hoped for her to come.
彼は彼女が来ることを願った。
[4-6(force型)] force型。これが本物のSVOC文型をとる動詞である。
Oppression provoked the people to rebel.
圧制が民衆の反乱を呼び起こした。
She urged him to accept the offer.
彼女は彼にその申し出を受けるよう迫った。
[5]形容詞的用法
[5(形容詞的用法)]名詞句の後に置かれて名詞句を修飾または叙述する。不定詞が修飾または叙述する名詞句が不定詞にとって何なのかによって以下に分類される。
①不定詞の主語
②不定詞の目的語
③不定詞内の前置詞の目的語
④③において前置詞が常に省略される場合
⑤不定詞と同格
[5(形容詞的用法)-1(修飾・叙述する名詞句が不定詞の主語)]
[5-1-1(修飾する名詞句が不定詞の主語)]修飾する名詞句が不定詞の主語である場合、単純に関係代名詞節で書き換えられる。
I have no one to help me.→
I have no one who help me.
私には助けてくれる人がいない。
Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon.→
Neil Armstrong was the first person that ever set foot on the moon.
ニール・アームストロングは月面に足を踏み入れた最初の人だった。
She's the youngest person ever to swim the Channel.→
She's the youngest person that has ever swum the Channel.
彼女はイギリス海峡を泳ぎ渡った最年少の人だ。
[5-1-2(叙述する名詞句が不定詞の主語)]叙述する名詞句が不定詞の主語である場合、be+to不定詞の構文になる。
You are to decide that.(不定詞の主語が文の主語である)
君はそれを決めなければならない。
[5(形容詞的用法)-2(修飾・叙述する名詞句が不定詞の目的語)]
[5-2-1(修飾する名詞句が不定詞の目的語]修飾する句が不定詞の目的語である場合、進行形不定詞、完了形不定詞を除いて、「~するべき」という should と等しい意味をもつ。
There are many difficulties to overcome.→
There are many difficulties that we should overcome.
乗り越えるべき困難がたくさんある。
I have no time to lose.→
I have no time that I should lose.
無駄にするべき時間はない。
[5-2-1-1(進行形不定詞・完了形不定詞の意味)]進行形不定詞は予定を表し、完了形不定詞は過去または完了を表す。
The man /to meet/to be meeting/to have met/ is Mr. Brown.
/会うべき/会うことになっている/会った人/はブラウンさんです。
[5-2-2(叙述する名詞句が不定詞の目的語)]叙述する名詞句が不定詞の目的語である場合、be+to不定詞の構文になる。
That is for the court to decide.(for は不定詞の主語を示す。叙述する that が to decide の目的語である)
それは裁判所が決めるべきことだ。
上の構文は以下とは異なる。
It is not for me to judge you.(it は形式主語。for は「~のために」という意味の前置詞)
君を裁くのは私の役目じゃない。
[5(形容詞的用法)-3(修飾する名詞句が前置詞の目的語)]修飾する名詞句が不定詞内の前置詞の目的語である場合。修飾する名詞句が広義の手段であることを表す。
She needs a friend to play with.
彼女には遊び友達が必要だ。
This shirt has no pocket to put things in.
このシャツには物を入れるポケットがない。
She is not a person to rely on.
彼女は頼れる人ではない。
[5-3-1(それらを関係詞+to不定詞を用いて書き換えると)]以下のようになる。格式体である。
She needs a friend with whom to play.
This shirt has no pocket in which to put things.
She is not a person on whom to rely.
[5-3-2(前置詞の任意の省略)]不定詞が修飾する名詞句が手段であり、不定詞の主語とも捉えられる場合、前置詞は省略されることがある。
He had no money to buy the ticket (with).(金が切符を買うともとらえられる)
彼は切符を買う金をもっていなかった。
I want some scissors to cut the paper (with).(鋏が紙を切るともとらえられる)
この紙を切る鋏が欲しい。
[5-3-3(前置詞の義務的省略)]④[5-3]において前置詞が義務的に省略され、手段だけでなく時間、場所も表す場合がある。
The time (at which) to go is 9:30.(時間を示す)
出発する時間は9時30分です。
The way (in which) to do it is this.(手段を示す)
そのやり方はこうです。
The thief had no car (in which) to escape.(場所を示す)
泥棒は逃走する車をもっていなかった。
[5(形容詞的用法)-4(不定詞が修飾する名詞句と同格)]
She had the misfortune to lose her only son.
彼女は一人息子を失うという不幸に見舞われた。
I had no occasion to speak French.
私にはフランス語を話す機会がなかった。
It is time for me to take a vacation.
= It is time I took a vacation.(that節 中は仮定法過去になる)
休暇をとってもいい頃だ。
[5-4(不定詞が修飾する名詞句と同格)-1(動詞または形容詞から派生した名詞)]を修飾する場合がある。
I have no wish to quarrel with you.=
I don't wish to quarrel with you.
私にあなたと喧嘩をするつもりはありません。
He showed a willingness to go.=
He showed that he was willing to go.
彼は喜んで行こうという気持ちを表した。
[6]副詞的用法
[6(副詞的用法)]動詞句または文、節全体を修飾するのが不定詞の副詞的用法である。意味または用法を以下のように分類できる。
①変化の方向、②目的、③結果、④感情の原因、⑤判断の根拠、⑥判断の有効範囲、⑦相関句、⑧文副詞、
[6(副詞的用法)-1(方向)]運動を含む変化の方向を表す。そもそもto不定詞の to の語源は 前置詞 to である。変化の方向を示すことは前置詞 to の最も基本的な機能だった。だから、変化の方向を表すことは to不定詞の最も基本的な機能である。SVC文型のCともとらえられる場合がある。
In time I came to love her.(SVC文型のCともとらえられる)
やがて私は彼女を愛するようになった。
He tends to be careless.(SVC文型のCともとらえられる)
彼は不注意になりがちだ。
How did you get to know him.(SVC文型のCともとらえられる)
どうして君は彼を知るようになったのか。
He made up his mind to go at once.
彼はすぐに行こうと決心した。
She consented to marry him.
彼女は彼と結婚することに同意した。
[6-1(方向)-1(動詞が表す動きの方向だけでなく、形容詞が表す動きの方向を示すことがある)]
She's anxious to go home.
彼女はしきりに家に帰りたがっている。
The boy was afraid to go out alone at night.
その男の子は怖くて夜一人で外出しようとしなかった。
[6-1(方向)-2(以下は感情の原因と間違えやすいが、方向を表す)]
I'll be glad to come.(方向)
喜んで参ります。
I will be interested to meet him.(方向)
私は彼に会いたいと思っています。
それに対して以下は感情の原因を表す。
I'm glad to see you.(原因)
お会いできてうれしいです。
[6(副詞的用法)-2(目的)]方向から発展して目的を表すようになる。
He feigned illness (in order) not to attend the wedding.
彼は結婚式に出ないように仮病を使った。
The priest held up his hand for them to be silent.
牧師は彼らが黙るように手を上げた。
[6-2(目的)-1(不定詞の主語)]目的を表す不定詞の主語について
[6-2-1-1(文の主語)]不定詞の主語が文の主語のときは、示す必要がないし示さない。
[6-2-1-2(文の目的語)]不定詞の主語が文の目的語になることもある。その場合も不定詞を表さない。
She sent him to the shop to buy bread.
彼女はパンを買うために彼を店に送った。
[6-2-1-3(上記以外では for を用いて不定詞の主語を示す。)]
The priest held up his hand for them to be silent.
牧師は彼らを黙らせるために手を上げた。
[6-2-2(in order to -, so as to -)]目的の意味を明確にするために、so as to不定詞, in order to不定詞を用いることがある。これらのうち、in order to不定詞は格式体で目的の意味を明確にする。in order to不定詞が文頭に来る場合もある。so as to不定詞は目的の意味が弱く、結果を表すこともある。
In order for liberal rights to be protected, armed forces sometimes need to be used.
自由権を擁護するためには武力が行使されなければならないことがある。
I had to shout so as to make myself heard.
私は聞こえるように大声を出さなければならなかった。
I hurried out so as to be in time for class.(結果)
私は急いで出たので授業に間に合った。
[6-2-3( not の位置)]否定の目的を表すために not を入れることができる。その位置はto不定詞の直前である。
She ran away so as not to meet him.
彼女は彼に会わないように逃げた。
It was hard for me to say those things―very hard. But I had to do it in order not to be taken back to the Lubiyanka.
それらのことを言うことは私にとってつらいことだった。非常につらかった。だが、ルビヤンカに連れ戻されないためには私は言わなければならなかった。
[6-2(目的)-4(形容詞的用法)]目的を表す不定詞の副詞的用法が形容詞的用法になり名詞を修飾することがある。
I want a case to keep my records in.
私はレコードを入れるためのケースが欲しい。
[6-2(目的)-5(目的を表すのに to不定詞と for動名詞の違い)]前者は特定の状況での目的を表し、後者は一般的な状況での目的を表し、名詞句を修飾するときに用途などを表しえる。
I want a case to keep my records in.
私はレコードを入れるためのケースが欲しい。
This is a case for keeping records in.
これはレコードを入れるためのケースです。
The dollar remains the currency for conducting international trade.
ドルは国際貿易などを行うための通貨として残っている。
[6(副詞的用法)-3(結果)]目的から発展して結果を表すことがある。目的と異なり無意志的動詞が不定詞になることがある。
He will live to be ninety.
彼は90歳まで生きるだろう。
I woke that night to find a neighboring house in flames.
その夜、私が目を覚ますと近所の家の一つが炎に包まれていた。
[6-3(結果)-1(慣用的表現)]以下のような慣用的発展がある。
- (,) only to -: ~したが結局~しただけだった。
- (,) never to -: ~して二度と~しなかった。
I ran all the way to the station, only to find that the train had left.
私は駅までずっと走ったが、結局、電車は出てしまっていた。
In 1980 he left England never to return.
彼は1980年にイギリスを去り、二度と戻って来なかった。
[6-3(結果)-1(慣用的表現)例外] only to不定詞 が「~するためだけに」という目的を表すことがある。
Some books are written only to make money.
カネ儲けのためだけに書かれる本もある。
[6(副詞的用法)-4(感情の原因)]感情を表す形容詞を修飾して、その感情の原因を示す。不定詞は一般に未来志向的だが、この用法は未来志向的ではない。
I am glad to see you here.
私はここであなたとお会いできてうれしいです。
He was shocked to hear the news.
彼はその知らせをきいて衝撃を受けた。
[6-4-1(完了形不定詞)]過去の事実であることを強調するときは完了形不定詞を用いる。
I am sorry to have missed him.
彼に会えなかったことが残念だ。
[6-4(感情の原因)例外]上と同じ glad であっても、以下は、[6-1]の方向を表し、未来志向的である。
I'll be glad to come.
よろこんで参ります。
[6(副詞的用法)-5(判断の根拠)]
She must be mad to dye her hair green.
髪の毛を緑色に染めるなんて、彼女は気が狂っているに違いない。
What a lucky fellow I am to have such a wife.
こんな妻をもつなんて、私はなんと幸運なんだろう。
What have I done to be looked at, like that?
そんなに見られるなんて、私が何をしたというのですか。
He would be naive not to consider at least the possibility that this situation involved a deadly disease.
この状況に恐ろしい病気が係わっている可能性を考慮しなかったとしたら、彼は経験不足ということになるだろう。
上の例文のように不定詞の否定形もありえる。それは不定詞の意味用法全般に言えることである。
[6(副詞的用法)-6(判断の有効範囲)]判断の有効範囲を表す。
He is easy to talk to.
彼は話しかけやすい。
This child is /quick/slow/ to learn.
この子はもの覚えが/早い/遅い/。
This was a shocking thing for Brezhinev to say who was a leader of an atheistic communist country.
それは無神論的な共産主義国の指導者であるブレジネフが言うこととしては衝撃的な言葉だった。
[6-6(判断の有効範囲)-1(慣用句)]となっている以下もこれに属する。
be able to -, be apt to -, be free to -, be welcome to -, etc.
Please feel free to use my bicycle.
どうぞ自由に私の自転車をお使いください。
Anyone is welcome to try it.
どなたでも自由にお試しください。
He is apt to forget.
彼はもの忘れしやすい。
[6(副詞的用法)-7(相関句)]判断の有効範囲からの慣用的発展である。過去時制では結果を含意する。つまり、現実にそうなったことを意味する。
too - to …:~するには~すぎる→あまり~で~できない
enough to …:~できるほど十分に~だ→十分~だから~できる
so - as to …:~できるほどとても~だ→とても~だから~できる
Allan was laughing too hard to stop.
アランは笑い過ぎて、笑いを止められないでいた。
Dick ran fast enough to catch the bus.
ディックは早く走ったので、バスに間に合った。
I was so fortunate as to win the prize.
私は幸運にも賞を取った。
[6(副詞的用法)-8(文副詞)]文全体を修飾し、文副詞の働きをするto不定詞。慣用句になっている。多くが発話様式副詞の働きをする。
To be honest, 正直に言って、
To be frank, 率直に言って、
To be brief, 手短に言って、
To be just, 公平に言って、
To tell the truth, 本当のことを言うと、
To say nothing of -, ~は言うまでもなく、(良くないことに用いる)
Not to mention -, ~は言うまでもなく、
Not to speak of -, ~は言うまでもなく、
To begin with, まず最初に、
To be sure, 確かに、
To judge from -, ~判断すると、
To make /matters/things/ worse, さらに悪いことには、
[6-8(文副詞)-1(独立)]文全体を修飾する文副詞に対して、不定詞が独立して驚き、憤慨、遺憾…などを表すことがある。古語である。
To think that we lived next door to him and never realised what he was up to!
隣に住んでいながら、彼が何をもくろんでいるのか分からなかったとは。
To think that the world's full of these creatures!
世間にはこんな奴らがいっぱいいるんだと思うとなあ。
[6-8(文副詞)-1(独立)-1(相関句)]さらに、O, Oh などに続いて、願望を表すことがある。古語である。
Oh, to be in England.
イングランドにいられたらなあ。
[6-8-1-1補足(Oh that, Oh for -)] O, Oh などに続いて願望を表す表現としては他に、Oh that 仮定法、Oh for - がある。古語である。
Oh that I had never seen it!
ああ、あんなものを見なければよかった!
O for a draught of vintage!
年代物のワインを一杯飲めたらな。
[7]完了形不定詞の意味用法
完了形不定詞の基本的な意味用法は以下の[7-1][7-2]である。
[7(完了形不定詞)-1(過去)]主動詞の時制より一つ前の過去を表す。
He seems to have seen her yesterday.
彼は昨日、彼女に会ったように見える。
She was sorry to have missed him.(彼女が残念だったのも過去だが、彼に会えなかったのはそれより一つ前の過去である)
彼女は彼に会えなくて残念だった。
[7(完了形不定詞)-2(完了)]主動詞の時制における完了、結果、経験、継続を表す。
He seems to have finished the job.(完了)
彼は仕事を終らせたように見える。
He seems to have been to Europe.(経験)
彼はヨーロッパに行ったことがあるように見える。
[7(完了形不定詞)-2-1(未来完了)] want, hope, などの未来志向の動詞の現在形を主動詞とするときは完了形不定詞は未来における完了を表す。それに対して、それらの過去形を主動詞とするときは、後述するとおり、不定詞は実現しなかった願望等を表す。
I hope to have finished the job by next Saturday.( hope は現在形)
私は次の土曜日までにその仕事を終えたいと思う。
I hoped to have finished the job by last Saturday.( hoped は過去形)
私は前の土曜日までにその仕事を終えたいと思っていたが、できなかった。
[7(完了形不定詞)-3(非現実)-1(義務、必要、意志等の助動詞)] should, ought to, would like to, need not, had better などの助動詞が推測以外の義務、必要、意志…などの意味をもつとき、助動詞+完了形原型不定詞が、実現/すべきだった/したかった/が実現しなかったことを表す。
You shouldn't have made a U-turn on a one-way street.
君は一方通行でUターンすべきでなかったのにした。
The man's identity ought not (to) have been disclosed.
その男の身元は公開されるべきでなかったのにされた。
I'd like to have seen the game.
= I'd have liked to see the game.
その試合を見たかったのに見れなかった。
You need not have quit your job.(助動詞 need の過去形は need である)
君は仕事を辞める必要がなかったのに辞めた。
You /could/might/ have told me!
私に言ってくれたらよかったのに言わなかった。
[7-3(非現実)-1(助動詞)-1(重複)]さらに、以下のような完了形原型不定詞と完了形to不定詞を重ねる表現さえ稀にある。これは誤用とされることもある。
I would have liked to have had a son.
私に息子がいたらよかったのだが…
[7-3(非現実)-2(推測の助動詞)] will, can, may, would, could, might, should, ought to などの助動詞が推測の意味をもつとき、助動詞+完了形原型不定詞で、過去のことまたは完了したことの推測、または、そう推測されたがそうならなかったことを表す。
They /could/should/ought to/ have arrived in London by now.
彼らは今頃、ロンドンに着いているはずだ。
I was very surprised to hear that. She should have passed the examination easily.
私はそれを聞いてとても驚いた。彼女は試験にやすやすと合格するはずだったのにしなかった。
[7-3(非現実)-3(本動詞)] be to -, want, intend, mean, hope, expect, need などの意志、欲求、予定、必要などを表す動詞の過去形+完了形不定詞で実現しなかったそれらを表す。
She intended to have called, but was prevented by a headache.
彼女は電話をするつもりだったが、頭痛のためにできなかった。
I was to have started work last week, but I changed my mind.
私は先週仕事を始めることになっていたが、気持ちが変わった。
The girl that I spoke of was to have married me two years ago.
私が話をした娘は二年前に私と結婚することになっていましたが…。
[7-3(非現実)-4(本動詞、過去完了形)]それらの動詞の過去完了形+to不定詞で同様の意味がある。こちらのほうが普通に用いられる。
I had hoped to catch the 8.30, but found it was gone.
8時半の電車に乗ろうと思っていたのだが、出てしまっていた。
[7-3(非現実)-4(本動詞、過去完了形)-1(重複)]さらに、不定詞まで完了形にすることさえ稀にある。これは誤用とされることもある。
I had intended to have written to him.
彼に手紙を書くつもりだったのだが…。
[7-4(→7-2-1)]それらに対して、[7-2-1]のとおり、want, hope などの未来志向の動詞の現在形+完了不定詞 は未来の完了を意味する。
I hope to have finished the job by next Saturday.
私は次の土曜日までにこの仕事を終えたいと思う。
[8]代不定詞
[8(代不定詞)]to不定詞において to だけが残ったものを代不定詞と呼べる。同一の動詞の繰り返しを避けるためにある。先行の動詞句または主節の動詞句全体の代用をする。
My son's funeral was held by the military together with those of a lot of other conscripts in Moscow. We hadn't seen his body. I didn't try to open the coffin myself. My father wanted to but the officers there told us not to. All along none of us were allowed to. We were not allowed to write on his gravestone that he'd died in Afghanistan, either. My father suspected that they didn't so much as make an effort to bring his body home. I didn't see him dead anyway. So even now I can't believe that he is dead but believe that he is alive somewhere in the world. I don't know whether to thank them or not.
息子の葬儀は他の多数の徴収兵の葬儀とともにモスクワで軍によって行われた。私たちは彼の遺体を見ていなかった。私自身は棺を開けようとしなかった。父はそうしたがったが、居合わせた将校たちが開けるなと言った。最初から最後まで私たちは皆、棺を開けることを許されなかった。彼がアフガニスタンで死んだと墓石に記すことも私たちは許されなかった。彼らは遺体を母国に運ぶ努力さえしなかったのではないかと父は疑った。ともかく私は彼が死んでいるところを見なかった。だから今でも私は息子が死んだことを信じられず、世界のどこかで生きていると思っている。彼らに感謝するべきなのか私には分からない。
[8-1(代不定詞が用いられない場合)]
[8-1(代不定詞が用いられない場合)-1(代不定詞も省略される場合)]希望、願望を表す動詞が時や条件の副詞節の中にあるときは代不定詞も省略されることが多い。
Come when you want (to).
来たいときに来なさい。
Come if you like (to).
来たければ来なさい。
Employees can retire at the age of 60 if they choose (to).
もし望むなら、従業員は60歳で退職できる。
[8-1(代不定詞が用いられない場合)-2( to不定詞が be と have を含むとき)]は、それらより後を省略する。
She hasn't been promoted yet, but she ought to be.
彼女はまだ昇進していないが、昇進するべきだ。
You've got more freckles than you used to have.
君は昔よりそばかすが多くなった。
[8(代不定詞)-1(代不定詞が用いられない場合)-3(原型不定詞)]を用いる場合は当然、代不定詞は生じない。
"Can you swim?" "Yes, I can."
「泳げるか」「泳げるよ」
[8-2(代不定詞の否定形は、not to である)]
She opened my drawer, though I told her not to.
彼女は私の引き出しを開けた。開けるなと言っていたのに。
[9] be to不定詞
[9( be to不定詞)]元来、取り決めを意味した。それから次の意味が派生した。
[9( be to - )-1(予定)]あらかじめの取り決めである。
We're to be married in June.
私たちは6月に結婚することになっています。
The Prime Minister is to visit Germany and France next month.
首相は来月、ドイツとフランスを訪問する予定である。
[9( be to -)-1(予定)-1( be の省略)]新聞の見出しなどでは be が省略されることがある。
PRIME MINISTER TO VISIT INDIA NEXT MONTH
首相、来月訪印の予定
[9( be to - )-1(予定)-2(yet, still→まだ~ない)]/yet/still/が入ると「まだ~ない」という意味になる。
The worst /was/had/ /yet/still/ to come.
最悪の事態はまだ来ていなかった。
[9( be to-)-1(予定)-3(完了形不定詞→非現実)]/was/were/ to完了形不定詞 で実現しなかった予定を表す。
I was to have started work last week, but I changed my mind.
私は先週、仕事を始める予定だったが、気が変わった。
[9(be to -)-2(義務)]権威をもつものからの一方的な取り決めである。
These tablets are to be kept out of touch of children.
この錠剤は子供の手の届かない所に置くこと。
They told me I was to report back the next day.
明日、報告するようにと彼らは言った。
[9(be to -)-2(義務)-1(主語+be の省略)]主語+be動詞が省略されることがある。
To be taken three times a day before meals.
1日3回食前に服用すること。
[9(be to -)-3(運命)]神の取り決めや自然法則である。
Little did young Lincoln know that he was to become President of the United States.
若きリンカーンは自分がアメリカ合衆国大統領になるとは夢にも思わなかった。
[9(be to -)-4(可能)]受動態で可能性を表すことが多い。
That is not to be denied.
それは否定できない。
The man was nowhere to be seen.
その男はどこにも見当たらなかった。
Mothers are more certain than fathers that their children bear some of the same genes as they do. It is therefore to be expected that fathers will put less effort than mothers into caring for children.
子供たちが自分たちがもつ遺伝子と同じもののいくつかをもっていることを母親は父親より確信できる。だから、父親は母親より子育てに努力しないということは考えられる。
[9(be to -)-5(意志)]条件節の中で意志を表すことが多い。
If we are to be friends, you must call me Leslie.
友達でいたいならレズリーと呼んでくれ。
[9-6(「万一~なら」という意味の仮定法の If S were to不定詞)] と区別すること。
[9-7( be to - の形をとるが、to不定詞が目的を表す副詞的用法である)]ことがある。
The letter was to announce their engagement.
手紙は彼らの婚約を知らせるためのものだった.
[9-8( beの過去形+to have 過去分詞 )] beの過去形+to have 過去分詞 になると、「~の/予定/義務/だったが~しなかった」という実現しなかったことを表す。
I was to have started work last week, but I changed my mind.
私は先週仕事を始めることになっていたが、気持ちが変わった。
[9(be to -)-9(慣用句)]以下の慣用句がある。
[9-9-1( be yet to-)]/be/have/ /yet/still/ to不定詞 で「まだ~しなければならない」→「まだ~していない」という意味になる
The worst was yet to come.
最悪の事態はまだ来ていなかった。
The influence is yet to be fully evaluated.
その影響はまだ完全に評価されていなかった。
I have yet to hear the story.
私はまだその話を聞いていない。
He has still to learn good manners.
彼はまだ礼儀作法を身に着けていない。
[9-9-2( remain to-)] remain to不定詞 でも上と同様にして「~しなければならないように放置されている」→「まだ~していない」という意味になる。
Those states asserted that the question of the status of Taiwan remained to be settled.
それらの国は台湾の地位の問題はまだ解決されていないと主張していた。
[9-9-3( be about to-)] be about to不定詞 「今にも~しそうである」という意味で近未来を表す。
Sit down everyone. The film's about to start.
みんな,座って.映画は今始まるところです。
[9-9-3-1( be not about to-)]否定形 be not about to不定詞 は「~するつもりは全くない」で否定の意志を表す。
I've never smoked in my life and I'm not about to start now.
生まれてタバコを吸ったことないし、これから始めるつもりも全くない。
[10]原型不定詞を用いる場合
[10(原型不定詞を用いる場合)]原型不定詞は to不定詞にあるような名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法をもたない。①助動詞とともに用いられるか、②一部の慣用的表現の中で用いられるか、③知覚動詞とともに用いられるか、④使役動詞とともに用いられるだけである。仮定法現在、命令法でも原型不定詞と同一のものが用いられるが、それらは不定詞に含まれない。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)]①be, have, ought, used を除く助動詞の後で
ここでは原型不定詞を使わない be, have, ought, used の例文を挙げる。
I am studying German.(進行形、現在分詞をとる)
私はドイツ語を勉強している。
The city was destroyed.(受動態、過去分詞をとる)
その都市は破壊された。
I have read the book.(完了形、過去分詞をとる)
私はその本を/読んでしまった/読んだことがある/。
I have to read the book.(義務必要、to不定詞をとる)
私はその本を読まなければならない。
You ought to read the book.(義務必要、to不定詞をとる)
君はその本を読むべきだ。
I used to play tennis a lot in my school days.(過去の状態・習慣、to不定詞をとる)
私は学生時代はテニスをよくしたものだ。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)]助動詞と原型不定詞を用いる慣用表現
/had better/had best/would better/ 原型不定詞
/would /rather/sooner/as soon/ 原型不定詞 /than/as/ 原型不定詞
/may/might/ well 原型不定詞
/may/might/ as well 原型不定詞( as 原型不定詞)
cannot (help) but 原型不定詞
do nothing /but/except/ 原型不定詞
などがある。
[10-1-1-1(had better 原型不定詞)]/had better/had best/would better/ 原型不定詞。「~したほうがよい」という相手より経験豊かなものとしての忠告の意味があり、目上の人には使わないほうがよい。
[10-1-1-1-1( had better の had は略式体でよく省略される)]
"I reckon I better stay," she said.
「私は留まったほうがいいと思う」と彼女は言った。
[10-1-1-1(had better 原型不定詞)-2(否定形は原型不定詞の前に not を付ける)]
You'd better not say that.
それは言わないほうがよい。
[10-1-1-1(had better 原型不定詞)-3(否定の疑問形)]は二通りあり、意味が異なる。
Hadn't we better leave?
俺たち、去ったほうがいいんじゃないか。
Had we better not leave?
俺たち、去らないほうがいいんじゃないか。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)-2( would /rather/sooner/as soon/ 原型不定詞 /than/as/ 原型不定詞)]「~するよりむしろ~したい」。
I /would rather/would as soon/ die /than/as/ surrender.
降伏するぐらいなら死にたい。
Wouldn't you rather live in the country?
田舎に住んだほうがいいと思わないかい。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)-3-1(/may/might/ well -)]助動詞の章で述べる。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)-3-2( /may/might/ as well + 原型不定詞 (+ as + 原型不定詞)]助動詞の章で述べる。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)-4( cannot (help) but 原型不定詞)]「~せざるをえない」。cannot help 動名詞 の米略式体である。
I /can't help laughing/can (help) but laugh(米略式)/ at her.
彼女を笑わずにはいられない。
[10(原型不定詞)-1(助動詞と)-1(慣用表現)-5( do nothing /but/except/ 原型不定詞)]「~するだけである」
She did nothing /but/except/ cry at the sight of the ruins.
彼女はその廃墟を見て泣くばかりだった。
[10(原型不定詞)-2(その他の慣用表現)]
[10(原型不定詞)-2(その他の慣用表現)-1( A as well as B )]については原型不定詞は必須ではない。 A , B の条件を説明する。
①「BだけでなくAも」「Bと同様にA」という意味で、as well as が相関接続詞で等位接続詞であるときは、A と B が文法的に等価ならよい。ただし、B が主語+動詞 となることは不可である。この意味の as well as において as が前置詞であるときは、B は動名詞でなければならない。A, B が主語になるとき、動詞の人称はAと一致する。
②「同じぐらい上手に」という意味では、as well as は通常の比較表現であり、as は接続詞であり、B が主語+動詞 になることも可。
He washes the dishes as well as /cooks/cooking/×he cooks/.①
彼は料理をするだけでなく皿も洗う。
He washes the dishes as well as /cooks/cooking/he cooks/.②
彼は料理と同じぐらい皿洗いが上手だ。
She can cook as well as sew.①(この場合は助動詞の後に来ているので文法的に等価にするためには原型不定詞でなければならない)
彼女は縫物だけでなく料理もできる。
We are repairing the roof as well as painting the walls.①(文法的に等価にするためには現在進行形の現在分詞でなければならない)
わたしたちは壁にペンキを塗るだけでなく屋根の修理もしている。
I am diligent as well as /he/×he is/.①=
I as well as he am diligent.( A as well as B において人称は A と一致する)
彼と同様に私も勤勉だ。
[10(原型不定詞)-2(その他の慣用表現)-2( go 原型不定詞)] 「~しに行く」とい意味では、go+to不定詞、go+現在分詞の他に、go+原型不定詞、go+and+動詞も可能である。等位接続詞 and で結ぶときは go と動詞は文法的に等価でなければならない。
I went see him.(過去形+原型不定詞)=
I went and saw him.( and で結ぶときは文法的に等価でなければならず、この場合は see は過去形でなければならない)
私は彼に会いに行った。
I'll go and get the phone.(この場合は助動詞の後なので文法的に等価にするためには get は原型不定詞 でなければならない)
僕が電話をとりに行くよ。
I've gone and cut the piece too short.(過去分詞 and 過去分詞)
私はそれを短く切り過ぎてしまった。
She often goes and sees movies.(現在形 and 現在形)
彼女はよく映画を見に行く。
[10(原型不定詞)-2(その他の慣用表現)-3(主語が do を含むとき)]主語が do を含み、不定詞が be動詞の補語になるとき、英米で原型不定詞が用いられることが多い。to不定詞を使用するのは古語である。ただし、主語に-ing(現在分詞または動名詞)があるときは補語の動詞も-ingにする。
All you have to do is (to) study as hard as you can.
君がしていればいいのはできるだけ勉強することだけだ。
The best I could do was (to) cheer him up.
私はせいぜい彼を元気づけることしかできなかった。
All you do is sneer at me.
あなたはわたしをせせら笑うことしかしない。
What she was doing was correcting the proofs.(一番目の -ing も二番目の -ing も現在分詞)
彼女がしていたことは試し刷りを校正することだった。
[10(原型不定詞)-2(その他の慣用表現)-4( to不定詞 rather than /to不定詞/原型不定詞/)] prefer は通常、prefer A to B の形をとるが、不定詞を比較するときは、to不定詞 rather than /to不定詞/原型不定詞/とする。
She preferred to stay at home rather than (to) go out.
彼女は外出するより家に居ることを好んだ。
[10(原型不定詞)-3(知覚動詞と)]③ see, hear, feel などの知覚動詞とともに用いる。
They saw him kick her.
彼らは彼が彼女を蹴るのを見た。
[10-3(知覚動詞)-1(現在分詞、過去分詞)]原型不定詞を用いると現在形または過去形の意味になる。原型不定詞の代わりに、現在分詞、過去分詞を用いるとそれぞれ、進行形、受動態の意味になる。
They saw him kicking her.(進行形の動作の反復の意味)
彼らは彼が彼女を(繰り返し)蹴っているのを見た。
They saw her kicked by him.(受動態の意味)
彼らは彼女が彼に蹴られるのを見た。
[10-3(知覚動詞)-2(文全体が受動態になるときは原型不定詞は to不定詞になる)]
Nobody ever heard him say "thank you" in his life.→
He was never heard to say "thank you" in his life.
生涯、彼が「ありがとう」というのを聞いた人は誰もいなかった。
[10-3(知覚動詞)-2(受動態)例外] watch, listen to などの注意を伴う知覚を表す動詞では受動態でto不定詞にならず、現在分詞になる。
They watched him steal into the house.→
He was watched stealing into the house.
彼はその家に忍び込むところを見られた。
[10(原型不定詞)-4(使役動詞)]④使役動詞で、原型不定詞を用いるのは let, make, have、to不定詞を用いるのは get, cause, bring, leave, etc. 原型不定詞とto不定詞の両方をとりうるのは、help, know。ただし、know については、否定形の完了形(経験)で「~なんて見たことも聞いたこともない」という意味でのみ、原型不定詞が可能である。
Mother let me go to the dance.(許容)
母は私にダンスパーティーに行かせてくれた。
I won't have you tell me what to do.(使役)
私がどうするかをどうのこうの言わせないぞ。
He had a man steal his wallet from him.(受動)
彼は財布をある男に盗まれた。
This book will help you (to) understand Japanese grammar.(促進)
この本は日本語文法を理解するのに役立つでしょう。
I have never known a horse (to) eat fish.(経験)
馬が魚を食べるなんて見たことも聞いたこともない。